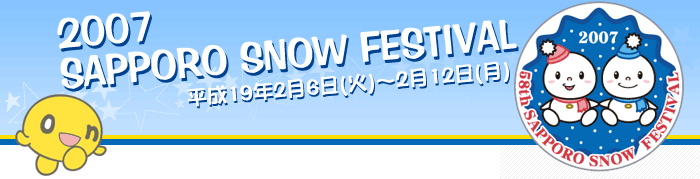NEXT
09:55
マル得JAPAN GOLD
10:25
アナちゃん
13:45
テレビショッピング
14:15
アナちゃん
14:18
笑う人には福来たる
14:48字
相棒セレクション 相棒11 #12【再】
24:21
とろサーモンのクズメンタリー
24:51
ウェザータイム
24:56
やすとものいたって真剣です ニッチ大好物グルメ「なす」名店巡り&決勝激突コンビ
25:56
アナちゃん
26:01
U字工事の旅!発見 【たいらや】
26:31
アナちゃん
26:36
ウェザータイム
26:41
ヒザにも!腰にも!ヒザこし健康源!
27:11
朝までN天
04:24
オープニング
04:25
買いドキッ!セレクション
04:55
グッド!モーニング
|
トップ>雪像説明
雪像説明
大雪像「国宝 彦根城」完成予想模型
『国宝 彦根城』は、井伊直弼など江戸幕府の中核となる人物を輩出した徳川家譜代大名筆頭の彦根藩主・井伊氏の居城でした。 徳川四天王の一人である井伊直政が、関ヶ原の戦いの功賞として石田三成の領地を拝領して佐和山城主となり、ここに彦根藩の基礎を築きました。戦場では赤具足を身に纏い「井伊の赤鬼」と勇名を馳せた直政でしたが、銃創が原因で病死します。嫡男・直継は父の遺志を継ぎ、慶長9年(1604年)に新たな場所・彦根山に城郭建設を着工します。この築城事業は幕府管理の下に行われた天下請負で、幕府から3人の公儀御奉行が派遣され、周辺の12大名の応援を得ての大工事でした。慶長12年(1607年)頃には天守が完成し、直継が彦根城主として入城、彦根藩の始まりとなりました。 
築城から400年。
今も変わらぬ気品と威容を誇る。 (彦根市) 彦根城天守は比較的小ぶりな三層三階の望楼型で、「切妻破風(きりづまはふ)」「入母屋破風(いりもやはふ)」「唐破風(からはふ)」を巧に配し、2階と3階には「花頭窓(かとうまど)」、3階には高こう欄付きの「廻縁(まわりえん)」をめぐらせるなど外観に工夫を凝らし、変化にとんだ美しい姿を見せています。「牛蒡積み」といわれる強固な石垣の上にそびえるこの天守は、大津城から移築された可能性があり、前身は四層五階であったようです。築城当時は周辺の城からの移築などで急造されたとも言われています。 その後、弟・直孝が家督を継いで2代目藩主となり、表御殿の造営、城郭改造などを経て、1622年に彦根の城下町が完成しました。天守は昭和27年に国宝に指定されました。現存する国宝の天守は、彦根城の他に姫路城、松本城、犬山城だけです。 「桜田門外の変」で井伊直弼は斬殺されましたが、彦根城は築城から明治維新後の廃藩置県まで一度も戦を経験することなく、井伊氏14代が彦根城主として存続しました。琵琶湖北東湖岸にたたずむ「彦根城」は現在もその威容を誇り続け、2007年に築城400年を迎えます。 「アイスブロック工法」という独自に開発した技法を持つ陸上自衛隊第11師団第18普通科連隊と、第11戦車大隊、第11施設大隊、第11通信大隊の共同制作による精緻な「彦根城」に加え、大雪像の右前には、彦根城築城400年祭のマスコット「ひこにゃん」も登場します。 *別名 金亀城(コンキジョウ)
|
|||||||||||||||||||