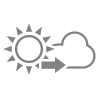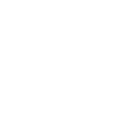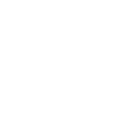札幌市内には、まだ雪がうず高く積もっていた3月の中旬のある金曜日。
私と嬉野先生、そして四宮Pの3人は午前中で仕事を切り上げると、車に乗り込み、道央自動車道を千歳方面へ向け走り出した。
これから、「あるお芝居」の視察に向かうのである。
「ナックスの皆さんとお芝居をやる」
そう決まった時、事務所の社長でもあるミスターから、こんなアイデアが出た。
「テント芝居なんてどうですか?」
テント芝居。一般の劇場を使うのではなく、文字通り「テント」を建てて、そこで芝居を見せる。有名なものに「唐十郎の紅テント」なんてのがある。演劇に関して素人の私も、その名前ぐらいは聞いたことがある。演劇には多少のうんちくを持つ嬉野先生によれば、それは、60~70年代前半のいわゆる全共闘時代、芝居と言えば「アングラな時代」の象徴的な存在であったという。
だから本来「テント芝居」というのは、そんな反体制的な匂い漂う、アウトローな雰囲気を持つものなのかもしれない。
しかし私は「テント芝居」と聞いて、全く違うことを思い浮かべていた。
幼少時代を過ごした山間の町。秋の祭りには青年団の素人芝居のような、まぁ「出し物」が町の公民館で披露されていた。「テント」ではなくあくまでも公民館なんだけれど、ゴザが敷かれただけの客席は粗末なものだった。それと、いつだったか大きな町で一度だけ見たことがある「サーカス小屋」。それはどうにも「楽しい」というより「あやしい」空気に包まれていた。
この2つの記憶が足し算されたような、どこか「懐かしい風景」。
「テント芝居」と聞いて、そんなものが思い浮かんだ。
そして、こう思ったのだ。
芝居ってのは、なんかこう弁当でも食いながら、もっと気楽に、あぐらでもかいて、やんやの喝采とともに笑って見られる、そしてどこか怪しげな、そんなもんじゃないのかな。
だから、そう。「テント芝居」なんてのは、まさにピッタリじゃないか!
想像してみよう。
普段はなにも存在しない場所に、忽然と現れる天幕(テント)小屋。
中はどうなっているのか、全く見えない。
怪しいったらない。
夕暮れが近づくと周りには薄灯りがともされ、そんな中、大勢の人々が行列をなして、その天幕小屋に吸い込まれていく。
一体、中ではどんなことが始まるのか。
一体、どんな出し物が披露されるというのか!
「う~む!見たい!」
怪しくもあり、楽しい出し物。
「でも作るのはオレだ。なんだ?なにをやるんだ・・・」
自問自答しながら宙を仰ぐ。
その時だ。
テレビから、やけに押しの強い声が聞こえた。
どうやら芝居の告知CMらしい。
画面を見る。
オヤジがニッコリ笑いながら言った。
「登別で、待ってるぜ」
沢さんである。沢竜二先生である。
「・・・これだ」と思った。我々が目指すべきは「これだ」と思った。
あやしい。文句なくあやしい。でも、おもしろそうだ。
沢竜二。ご存知、沢さん。旅一座の座長である。日本各地を巡業する昔ながらの人情芝居で、北海道の温泉場にも必ず年に数回いらっしゃる。梅沢富男先生が、その「妖艶さ」で世の女性を虜にしたとするならば、沢先生は、あくまでも「男気」。鋭いながらもどこか優しいその眼差しに、女性の心はかく乱される。竜二の瞳にブロークンハート。あやしいのである。
3月中旬のある金曜日。
私と嬉野先生、そして四宮Pの3人は、道央自動車道をひた走っていた。
目指すは登別温泉・ホテルまほろば!
「沢竜二の旅役者・座長大会」と銘打った「人情芝居」が開催されているのである。
我々は、「旅一座」のなんたるか。「人情芝居」のなんたるかを視察に行くのである。
さて、登別ともなれば無論、一泊。
しかし、今回の芝居公演は「北海道テレビ開局35周年」の正式な記念プロジェクト。遊び半分、物見遊山な気持ちで温泉場に行ったのでは、HTB全社員に対して示しがつかない。我々はプレッシャーを感じながらも、夜の観劇に備え、早めに宿に入り、浴衣に着替えるのももどかしく、早々に湯につかり、贅を尽くした部屋出しの夕食に舌鼓を打ち、一杯ひっかけて、万全の態勢で芝居視察に臨んだのである。
午後8時。ほろ酔いかげんで、芝居会場へと足を運ぶ。「会場」とは言ってもそれはホテル内にある「舞台付きの宴会場」である。そこに座布団が敷き詰められ、両サイドには簡単な照明機材。無論、四宮Pを含め我々3人とも浴衣姿である。会場はほぼ満席。大部分は我々と同じ浴衣姿の泊まり客であるが、中には私服の方もチラホラ見える。特に最前列付近には私服の熟女数人が陣取っている。
さて今夜の演目は「無法松の一生」。九州の炭鉱に生まれた、ひとりの無骨な男の物語である。出し物は日によって違うらしいが、どれも中身は知らずとも一度は耳にしたことがある「お馴染みのタイトル」がラインナップされていた。
かくいう私も「無法松の一生」という題名は知っているが、話の中身はまったく知らない。ただモノクロ映画の1シーンで、無法松さんがふんどし一丁で太鼓を乱れ打ちしているのを見たことがある。
(もしかして沢さんも、乱れ打つのだろうか・・・)
いやがおうにも期待は膨らむ。私ですらこうなのだから、最前列の私服熟女たるや、「無法松」と聞いただけで、早くもブロークンなはずだ。
そうこうしていると宴会場の照明がぱちぱちと消され、薄暗がりの中、スピーカーから演歌調の音楽が鳴り響いた。いよいよ開演である。
芝居の中身について詳しくは言わないが、開演から20分で、私の斜め前のおばちゃんはハンカチを取り出して涙をぬぐっていた。
開演から「たった20分!」である。たったの20分で、沢先生はおばちゃんを泣かせたのだ。実際、それぐらい熱のこもった舞台なのである。
とにかく芝居は、見せ場の連続であった。決めゼリフになるとピンスポットがびしっと沢先生を照らし出す。先生はその丸いピンスポの中で、とにかく圧倒的な迫力で、泣いた。そう。おばちゃんも泣いていたが、それ以上に無法松が泣いていた。そして泣きながら、歌い出した。そう。歌うのだ。最初は正直戸惑ったが、嗚咽まじりに歌い上げる沢先生の歌声は、とてつもない強制力を持って観客のハンカチを濡らし続けた。
芝居はおよそ1時間で終わった。拍手喝采の中、沢先生が再び舞台に登場した。
「無法松の一生、いかがでしたでしょうか」
(いやぁ・・・よかったです)
「お馴染みの『沢式ミュージカル』でお送りいたしました」
(ミュ・・・ミュージカルだったのか!)
「普段は、2時間かかるお芝居ですが、今回は1時間に短縮してお送りいたしました」
(どっ!どうりで見せ場の連続だったんだッ!)
「さて、この後は休憩をはさみまして・・・」
(まだ、あるのか・・・)
「お楽しみ、歌謡ショーにまいりましょう」
(かッ・・・歌謡ショー!)
人情芝居は一転、その後は、1時間に渡り、役者さん達の歌謡ショーが繰り広げられた。客席からは、「おひねり」がチャリチャリと投げ入れられ、大いなる盛り上がりを見せた。最前列の私服熟女さんたちは、「待ってました!」とばかりに贔屓の役者さんの歌になると、花束やおひねりを乱れ撃ちした。(彼女たちは決してふんどし太鼓を待っていたのではなく、この歌謡ショーを待っていたのだ)
客が一緒になって舞台を盛り上げる、この「旅一座」ならではの光景は、まさしく「私が求めていたもの」に合致した。
「これだ!間違いない!」
私は早くも第1回目の視察で、芝居のコンセプト、方向性のようなものを見出したのだ。
チームナックスによる「笑いあり涙ありの人情芝居」。
そして、おひねり飛び交う「歌謡ショー」。
ただこれは、これまでの彼らの芝居とは「あまりにもかけ離れた方向性」ではある。
また、彼らのファン層も「多少年齢的に高い層をターゲットに」することになる。
しかし!見てみたい!
「ヨッ!大泉!」
「いよっ日本一!」
客席から掛け声が飛ぶ。
「ケンちゃんシブイ!」
「シゲちゃんカッコイイ!」
「モリちゃんでかい!」
「タクちゃんはなれてる!」
私の頭の中には、ちょんまげのズラをかぶった5人が、ぐるんぐるん回る派手な演出のスポットライトを浴びて、「せいやッ!せいやッ!」言いながら、ふんどし一丁で太鼓を乱打する勇ましい姿が目に浮かんだ。
「これでいこう・・・」
そう決めかけた時、四宮Pが言った。
「まぁ、これはこれとして・・・来月、もうひとつお芝居を見に行きませんか?」
「梅沢先生ですか?」
「いや・・・」
「浅香光代ですか?」
「いやいや・・・」
「なんですか?」
「シェイクスピアです」
「は?」
「蜷川幸雄のシェイクスピアです」
「蜷川・・・世界の蜷川ですかッ!」
「そうです」
蜷川幸雄。演劇ド素人の私でも、その名前は知っている。
シェイクスピア。もちろん知っている。ロミオとジュリエット・・・それから・・・べ、ベニスの商人!それから・・・まぁ、いろいろ知っている。演劇といえば、もうシェイクスピアだ。当たり前だろう。
そして蜷川幸雄といえば、そのシェイクスピアの本場・英国でも公演を行い最高の評価を得ている世界的な演出家だ。
「その、蜷川幸雄のですね、『ぺリグリーズ』というシェイクスピア劇が、来月やるんですよ。見に行きませんか?」
「そうですか・・・札幌ですか?」
「新潟です」
「に、新潟?どうしてまた・・・」
「なんか立派な劇場があるんですって。新潟に。行きますか?」
「うーむ・・・しぇークスピアかぁ・・・」
正直、私は興味がなかった。シェイクスピアにおひねりは飛ばない。派手なライトがぐるぐる回らない。当然、ふんどし太鼓もない。第一、おもしろかねぇよ。
「それがね、おもしろいんですよ!すっごく!3時間ぐらいやるんだけどね・・・」
「3時間も・・・」
シェイクスピア3時間はキツイ。
しかし、四宮さんは興奮してしゃべり続ける。
「僕、実はこの前出張の時に東京で観たんですよ。でもね、もう一回見たい!とにかく藤やんにもうれしーにも、一度、見て欲しい!」
そこまで言われては・・・まぁ新潟なら、魚も美味いし、米も美味い。
「じゃ、行きますか。新潟」
我々3人は、翌4月末、新潟へと飛んだ。
そして・・・観た。
蜷川幸雄演出。シェイクスピア作。「ぺリグリーズ」。
私は・・・私は、生きてて良かった!
蜷川幸雄はすごい!シェイクスピアはすごい!芝居ってすごい!
新潟の劇場で、私は興奮しまくっていた。この感動をどう伝えればいいのだろうか。
そうだな。芝居が始まって1時間半。途中に休憩時間があった。
ロビーに出てタバコを一服しながら、私は心からこう思った。
「あと1時間半、まだこの芝居を観ることができるなんて、オレはなんて幸せなんだ!」
大げさでなく、本当にそう思った。みんなも機会があれば、いや、機会なんかなくとも!生きているうちに絶対に観るべきである。
こんな経験は初めてだった。
確かに映画やドラマを見て、幸せな時間を過ごしたことはある。しかし、やはり実際に役者が目の前で演ずる芝居は「全然!違う!」。
なんというか、「芝居の本質」。テレビなんか絶対にかなわない「芝居の強さ」を見た気がした。
蜷川先生の演出は、とにかく「楽しませること」に徹していた。とにかく「エンターテイメント」に徹していた。難しくなんかない。とてもわかりやすい。テンポがいい。圧倒的な迫力がある。そしてとにかく楽しい。そして最後には、自然に涙がこぼれた。
芝居が終った時の、観客の拍手の音は忘れられない。あれは、「お約束の拍手」じゃない。「終ったね。面白かったよ」なんていう生半可な拍手じゃない。観客全員が心の充足感を両手に込めて、震えるように拍手していた。あんな拍手の音を、私ははじめて聞いた。
これは「芝居の頂点」であると思う。
我々は、蜷川幸雄のシェイクスピアを目指す!
さらに!ある意味、沢竜二も・・・目指す!
「シェイクスピア」と「旅一座」の融合だ。
できるかどうか、んなもん!やってみないとわからない。
「水曜どうでしょう」の藤村忠寿と嬉野雅道。
そして、大泉洋!森崎博之!佐藤重幸!安田顕!音尾琢真!の「チームナックス」。
2003年10月10日。
HTBの駐車場に巨大な天幕小屋が出現する!
我々の名は・・・「水曜天幕團」(すいようてんまくだん)
出し物は、本格時代劇!「蟹頭十郎太」(かにあたまじゅうろうた)
公演内容詳細は8月1日(金)発表!
イメージCMも同日からO.A!
うーむッ!乞う!ご期待ッ!
NEXT
16:25
SDGs劇場 サスとテナ みんなで豊かになるには?
17:55
ウェザータイム
21:54
ウェザータイム
24:30
ウェザータイム
24:35
探偵!ナイトスクープ 【修羅場!?】父に夫を殴ってほしい&真栄田探偵が怖い15歳…
26:30
ウェザータイム
26:35
ドラマ「Solliev0」 第4話
27:05
アナちゃん
27:10
買いドキッ!セレクション
27:40
テレビショッピング
04:10
ダイレクトテレショップ
04:40
イイものショッピングゥ~!
05:10
人生100年時代を元気に過ごす秘訣大公開スペシャル!
05:40字
あなたとHTB
10:00字
題名のない音楽会
10:30
テレビショッピング