TOP > HTBについて - あなたとHTB
あなたとHTB
このページは令和7年12月28日放送分から引用しています。
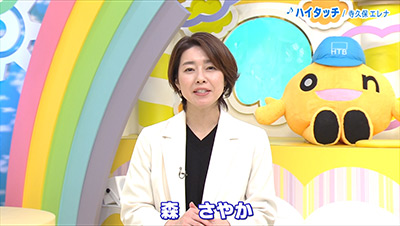
森さやかアナウンサー
おはようございます。「あなたとHTB」の時間です。
「あなたとHTB」は、視聴者の皆様とともに、
より良い番組作りと放送のあり方を目指す番組です。
まず、10月の第578回放送番組審議会で審議された
『HTBノンフィクション「看護師になりたかった…
~届かぬ叫び 沈黙の行政~」』について、委員の意見をご紹介します。
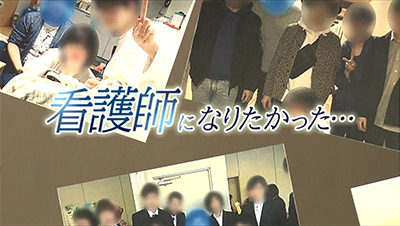
HTBノンフィクション「看護師になりたかった…~届かぬ叫び 沈黙の行政~」
この番組は、道立江差高等看護学院で起きた、
教師によるパワーハラスメント問題を追ったものです。
道は第三者調査委員会のパワハラ認定を受け、一度は謝罪したものの、その後一転してパワハラを否定。解決の道が見えない中、
番組では多くの関係者の証言を集め、問題の真相に迫りました。
この番組に対して、番組審議会の委員から出た意見から
評価された点を紹介します。
・全体として、取材の丁寧さと問題の本質を突く構成力が際立っていたと思う。被害者の尊厳を守りつつ、問題を浮き彫りにしたこの番組は高いジャーナリズム精神に基づいていると評価した。
・人の命を支える看護師を育てる学校なのに、それを志して入学してきた青年が自ら命を絶ってしまうとは、あまりに悲痛な出来事。取材班が、お母さんや友人、当時を知る学校関係者などにとても丁寧に取材を重ねてきたことが、番組全体から伝わってきた。
・道立の看護学校で生徒が自死した背景にハラスメントがあったこと、それに対する北海道の対応が変遷し、ハラスメント被害に誠実に向き合っていないのではないか、との問題意識から作成されたドキュメンタリーであると思う。その問題意識を高く評価する。
・自死した生徒の親や複数の同級生、教師や元学校関係者への聞き取りや、裁判資料の閲覧などに基づいた番組作りは、多くの労力を割いて取材をしたことがうかがわれる内容だった。特に、教師や元学校関係者への取材は、このドキュメンタリーに迫真性と真実性を付与するものであった。
・番組で明らかにされた教員によるハラスメントの内容は信じがたいものだった。また、学生が不当な扱いを訴えたり、支援を求めたりできる仕組みが機能していなかったことにも驚かされた。
ここまでは評価点をお伝えしました。ここからは要望点・改善点です。
・第三者調査委員会の認定が事実であれば、ハラスメントの問題は教師の指導をめぐる問題ではなく組織的な問題である。なぜこの学院で教師によるハラスメントが常態化することとなったのか、大きな疑問が残った。
・地方病院の規模縮小を「看護師不足が原因である」というストーリーに仕上げていたが、実際のところは人口減少によって患者数が減っていることから、医療人材の不足だけが縮小の要因ではなく、経営上の要因もあるはず。地域医療の現状を多面的にとらえているのか疑問が残った。
・教師達の意識はどこにあったのだろうか。人材育成のため高い倫理観や道徳観を守ろうとして生徒に厳しい要求をしていたのか。だとしたら人格を否定する言葉を使っていたのはなぜか。昔ながらの教育方針に漫然と従っていたのか。こうした点を深掘りして欲しかった。
・番組を見て、「パワーハラスメント」という言葉が含む意味の幅について興味を持った。第三者調査委員会が扱う言葉と、北海道、学生、母親、そしてこの作品が扱う言葉。それぞれが「パワハラ」という言葉の意味の差をどう埋めるか。それぞれの立場からより具体的な言葉がもっと聞きたかった。
次に、11月の第579回放送番組審議会で審議された
「LOVE HOKKAIDO」について委員の意見をご紹介します。
「LOVE HOKKAIDO」は、まだ知られていない北海道の魅力を深掘り
しながら発信する番組です。10月に番組をリニューアルし、今回は、
新メンバーとなった3人のうち、北海道にゆかりのある高田秋さんとなまらあつしさんが、後志の余市町と仁木町を訪れました。
この番組に対して、番組審議会の委員から出た意見から評価された点を紹介します。
・番組MCが交代すると、番組の雰囲気が変わるものだなと改めて思った。前のコンビは「落ち着いた気分で視聴できた」という感想を言ったことがあるが、新しいものにチャレンジするんだという意気込みを感じた。
・余市と仁木の果物、ウイスキー、ワインとジビエ、特産豚と多彩な魅力がバランスよく配置されていた。ぶどう狩りの屋外、博物館内、レストラン内という3つの雰囲気が全く異なる風景の場面の切り替わりも番組全体にめりはりをつけていた。
・観光農園で、高田秋さんがぶどうを食べた瞬間の素直でまっすぐなリアクションは、視聴者の食欲を直撃するものだった。「私も食べたい」と思わせる説得力があった。
・ニッカウヰスキー余市蒸溜所では、歴史や製造工程といった専門的な内容を明快な言葉で伝え、視聴後に訪れてみたいと思わせる力のある構成になっていた。レストランの落ち着いた大人の空気感、こはく色のウイスキーの映像も美しく、秋の余市の雰囲気によく合っていた。
ここまでは評価点をお伝えしました。
ここからは要望点・改善点・提言です。
・新鮮味がなかった。MCのレポートは上手だが、BGM、テロップ、効果音の使い方は演出としての既視感を感じた。良くいえば「お約束」かも知れないが、悪くいえばありきたりで、工夫やチャレンジを感じることができなかった。
・蒸溜所で3種のウイスキーのテイスティングをする場面では、それぞれの味について説明するテロップ表示が短く、十分に情報が入ってこなかった。せめて、あと数秒表示してくれると、それぞれの香りや味がもう少し理解できたのではないか。
・この時代に、家にいるだけでなくちょっと出かけてみようというきっかけを作ってくれる、背中をそっと押してくれる番組は貴重。これからも、番組キャッチフレーズのように「北海道を再発見」させてほしい。
ここで、お知らせです。

青少年のためのより良い放送のあり方を考える
BPOの青少年委員会が「中高生モニター」を募集しています。
この制度は、全国の中高生から選ばれたモニターに、
テレビやラジオの番組について、
毎月、率直な意見を報告してもらうものです。
モニターの任期は、来年4月から1年間です。
詳しい内容は、BPOのウェブサイトをご覧ください。
あなたとHTB。次回の放送は、
来年1月開催の第580回における委員のご意見を紹介いたします。











