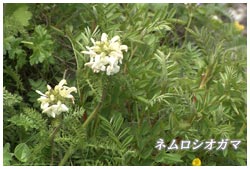|
日本最北の島、礼文島は、花の浮島と呼ばれる。
6月中旬、夏の花が見ごろを迎えている。 |
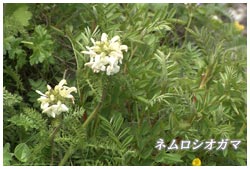 |
ネムロシオガマ。ゴマノハグサ科。20~40cm。
茎頂に密集した白花を付ける。 |
 |
レブンキンバイソウ。キンポウゲ科。15~80cm。
黄色の花弁に見えるのはがく片、5~13枚。 |
 |
ウニ漁は、夏の礼文の風物詩。
早朝から磯舟が出て、エゾバフンウニを水揚げる。 |
 |
オオカサモチ。セリ科。高さ1・5mにもなる。
花は茎の先に散形で、笠ののように大きく付く。 |
 |
チシマフウロ。フウロソウ科。80~100cm。
花は茎の先に集まり、2.5~3cmの薄紫色。 |
 |
ノビネチドリ。ラン科。
和名の延根千鳥は、地中の根が手形状にならずに延びる事に由来。 |
 |
ノビネチドリ。ラン科。花の一つ一つは
まるで翼を広げた天使のようだ。 |
 |
北海道北部に広がる夏のサロベツ原野。
大小の湖沼や日本最北の大湿原を抱える。 |
 |
エゾカンゾウ。ユリ科。50~70cm。
海岸草地や原野に黄色い花の群落をつくる。 |
 |
トキソウ。ラン科。15~25cm。
花は頂部に一つ。野鳥の朱鷺の色から名が付く。 |
 |
ツメナガセキレイ。セキレイ科。大きさ16.6cm。
夏鳥。黄色の眉と下腹が鮮やか。 |
 |
サロベツ原野の中心部は、小沼が点在する湿原が広がる。
湿原の大部分は泥炭地。 |
 |
ツルコケモモ。ツツジ科。細い針金のような茎で地上を這う。
花は下向き4枚の花弁が反り返る。 |
 |
ミズゴケ。ミズゴケ科。サロベツは、別名ミズゴケ湿原とも。
スポンジのように水をたっぷりと含む。 |
 |
モウセンゴケ。モウセンゴケ科。6~30cm。
食虫植物、毛先の粘液で虫を捕食する |
 |
ナガバノモウセンゴケ。エゾイトトンボを捕まえた。
自生地は、国内で4箇所。絶滅が心配される。 |
 |
エゾイトトンボ。オス。
食虫植物のナガバノモウセンゴケに捕まる。 |
 |
コタヌキモ。タヌキモ科。浅い水中に咲く。
水中の小さな虫を捕食する。 |
|