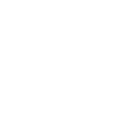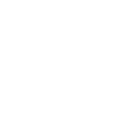お約束どおり、「びっくりうどん」のつづきである。
我々は、興奮状態のまま、物置を出た。考えを整理しなければならない。
(この「中村」なるうどん屋・・・いったい・・・)
私が腕組みをする横で、嬉野くんが、ハタと思いついたように言った。
「ここが・・・中村なんだよね?」
「えっ?」
そうだ。言われてみれば確かに、物置にかかったのれんに店名はなく、朽ち果てた看板には「インテリアカーテン・スマイル」と書かれてあった。
(うどん屋「インテリアカーテン・スマイル」か?・・・長いな。)
「いや!やっぱり中村だ!」
嬉野くんが、物置の横の住宅を指差して言った。
「ほんとだ・・・中村って書いてある」
玄関の表札には「中村」と、書かれてあった。
「そして、どうだ藤村くん・・・この家、わりと新しいぞ」
「確かに・・・」
物置の横に建つ中村さん家は、わりと新築で、そしてわりと立派だった。
「きっと、うどんで儲けたんだ」
「かもしれん・・・」
「なのにどうだ!肝心のうどん屋は、あの物置!」
「すごい!肝心の店舗には、一切投資してないじゃないか!」
「藤村くん!これはスゴイ!スゴイことだぞ!」
我々は、一気に「讃岐うどん」の、「讃岐うどん屋のなんたるか」を理解した。
我々の推論は、こうだ。
そもそも、「中村」には、「飲食店としての概念」が希薄なのだ。というより、もともと「うどん屋」なんかじゃなかったのだ。
それがいつのころからか、「中村さん家のうどんは美味い」なんて、ご近所で評判となり、それを聞きつけた好奇心旺盛なおっさんが、
「すんませんけど、うどん一杯食わせてもらえんかね?」
「ええですけど・・・でも、応接間では今おじいちゃんが寝とるけぇ・・・」
「いいの!いいの!そこの物置で食うから!」
「そうですか・・・じゃ、ネギを裏庭から・・・」
「いい!いい!わしが取ってくるけ!」
なんてな感じで、どんどん広まっていったのではないか。
だとしたら!これこそ「飲食店のあるべき、一番正しい形」ではないか!
「うまい」ことが、第一条件として整い、それを食った人々の勝手な熱意によって、「いつのまにやら飲食店」にされてしまった。
「中村」の成り立ちが、本当にそうなのかどうか、これは、あくまで我々の推論でしかない。
しかし、そう考えると、「物置」で、「看板」も出さず、「人目を避けるように」、というより「結果的に人目を避けちゃって」うどん屋を開業していること、その全てに合点がいく。
そして、この旅の終り・・・高松空港の本屋で「恐るべきさぬきうどん」全巻を見つけ、それを熟読した結果、我々の推論が、あながち誤りでなかったことを知った。
例えば、「どうでしょう」が「四国イチオシ」としてご紹介した「山越」さん。
ここも、元来「うどん屋」ではない。うどんの麺を製造する「製麺業」が本業だ。
まぁ、言ってみたら「工場」だ。
それが、いつの頃からか、
「山越さんのうどんはうまいなぁ。ちょっと作りたてを食べてみたいなぁ・・・」
「あぁ・・・ええですけど。でもウチは製麺屋ですからイスもないし・・・」
「ええ!ええ!そこらへんで立って食うから!」
そうして、イスがひとつ増え、ふたつ増え・・・、そのうち、
「天ぷらとかあるとうれしいなぁ・・・」
「あぁ・・・ほな、天ぷらも作りましょか」
「ほんまですか!ありがたいなぁ!」
結果、従業員が忙しく製麺するかたわらで、人々が行列を作り、うどんが茹であがると、かたっぱしからどんぶりに投げ入れ、天ぷらをのせ、店のあちこちで勝手に食う、という現在の営業形態に至ったのである。
「製麺所で、茹であがったばかりのうどんを食う」
これはもう、「絶対うまい!」に決まってるのだ。
私が、最初に「山越」の「かまたま」を食った時の衝撃は、はかりしれない。
世界中で食った、どんな料理も足元に及ばない。
たかが「うどん」。多分、離乳食の時から何千杯も食っている食い物だ。
「フォアグラというものを、初めて食いました。美味かったです」というのならわかる。
しかし、たかが「うどん」で、これほどの衝撃を受けるとは、考えてもいなかった。
あつあつ、茹でたての「つるぴかうどん」に、なま玉子を一個割り入れる。
カラカラカラっ!とかき混ぜると、ほどよく固まった玉子が、つるぴかを白濁した黄色に変えて、からみつく。
そこに、ペットボトルに入った特製のダシを、少し垂らして、一気に食う!
もう・・・もう!ダメだ!
味だの食感だの、ごちゃごちゃ言ってると、今すぐ四国に行きたくなる。
あれは、「うどん」じゃない。日本人なら、必ず脳天を打ち砕かれる「味覚の最終兵器」だ。
さらに驚くのは、こうした「看板も出さない」「ただ、みなさんが、うまいって言うから、とりあえず店にしてますの」という、あっぱれな「営業形態」をとる店が、「中村」「山越」に限らず、香川県内には、数多く存在しているという事実である。
決して、東京あたりの「隠れ家的フレンチの名店」とか「わたしだけが知っている!秘密のカフェーで午後のエスプレッソ!」なんて、ふざけたかくれんぼを売りにするこざかしい店とは違い、
「いや、隠れてるわけじゃなくてですね、もともと見えにくいトコにあるんです。どうも、すんません」
という、香川のうどん屋は、実にさりげなく、カッコイイのだ。
さらに!だ。まだあるぞ。
香川の「うどん屋」が素晴らしいのは、こうした「異空間でのびっくり店舗展開」だけでなく、ごく「一般的な店舗」においても、その「うまさ」に驚かされることが多々あるということだ。
我々は、「中村」のあとにも、もう一軒のうどん屋を訪ねた。(そうだ。この日は四軒行った。結局、寺には行かず、宿に入った)
訪ねたのは、善通寺の「山下」という店である。
「異次元」を体験してしまった我々だ。なんに対しても驚かないつもりでいた。
しかし、「山下」に着くと、ちょっと違う意味で驚いた。
驚いたと言うより、「その店舗形態に、落胆した」と言ったほうが正しい。
「山下」は、お世辞にもうまそうには見えない「国道沿いのドライブイン」のような外観を呈していた。
信頼のおける「うどんマップ」がなかったら、絶対に立ち寄らない店だ。
それが・・・うまいのだ。
うどんのコシがもう、絞め殺す気か!ってぐらいにスゴイのだ。究極のコシコシを味わいたいマニア諸兄は、悶絶必至の麺である。
後に「四国R-14」のロケで訪れた時、佐藤シゲが感涙にむせび、今でも「山下が忘れられない!」と、ことあるごとに言ってるらしい。
数百円で、人をこうも虜にしてしまう「讃岐うどん」。
香川の「うどん屋」は、いつも多くの人々で賑わっていた。
子供連れのお母さん。営業の外回りのついでにフラリと立ち寄るサラリーマン。じいさん、ばあさん。
500円あれば、うどんに天ぷらのせて、ガラスケースに並んだ「手作りのおいなりさん」も食える。
「札幌の人は、いつもラーメン食ってるんでしょ?」
食ってないよ。
「名古屋の人は、いつもきしめん食ってんでしょ」
食ってねぇ!
「香川の人は、いつもうどん食ってるんですか?」
はい!食ってます!
我々は「讃岐うどん」が、ただ「うまい」だけでなく、「地域に根ざした食文化」を正しい形で残している、非常に稀有な例であることを知り、今や「尊敬の念」を抱くに至った。
この、日本で一番小さな「香川」に現存する、日本で最も偉大な食文化。
外部にいる我々は、しかし、決して騒ぎ立ててはいけない。我々は、彼らが築いてきた食文化の恩恵を、少しだけ体験させてもらう身なのだ。
「100円のうどんを食いに、北海道から、飛行機で香川へ行く。」
人が聞いたらバカだと思うかもしれん。
しかし、これは貴重な体験であり、「価値ある旅」である。
・・・結局、我々はこの旅で、10軒近いうどん屋を巡り、そして、札幌に帰った。
嬉野先生が、ラストシーンを書き上げたのは、それからしばらくたってからのことだった。
【おわり】
この文章を、香川県民のみなさまと、そして、本当に「うどんを食うためだけに、飛行機で香川に通いつめたバカな男」・・・チームナックスリーダー・森崎博之に、捧げる。
NEXT
24:25
これ余談なんですけど… 鬼才堤幸彦監督ご来店!「SPEC」「TRICK」など名作の裏側
25:25
みやぞんのぶらり人情グルメ旅
25:45
ココホリケンケン
26:15
ウェザータイム
26:20
転生したらドラゴンの卵だった~最強以外目指さねぇ~
26:50
野生のラスボスが現れた! #5「野生の温泉が現れた!」
27:15
テレビショッピング
27:45
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
テレビショッピング
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
ダイレクトテレショップ
10:25
アナちゃん
13:45
アナちゃん
13:50字
科捜研の女 #9【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #17【再】