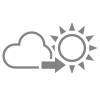NEXT
24:45
ウェザータイム
24:50
テレビ千鳥 ノブの演技が見たいんじゃ!!『地面師ノブ』
25:20
霜降り明星のあてみなげ せいや絶体絶命!?自転車のスゴ技で…?キャンプ企画です
25:50
アナちゃん
25:55
紫雲寺家の子供たち 第5話「Perhaps」
26:25
ウェザータイム
26:30
アナちゃん
26:35
イチおし!プレミアム
27:05
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
健康家族テレショップ
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
健康家族テレショップ
10:25
アナちゃん
13:45
まるっと健康生活
14:15
ビジネスウィークリー
14:20字
テレメンタリー「2024年度最優秀作品アンコール 生ききる~俳優と妻の夜想曲~」【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒19 #13【再】
![]()
- アトラソフ島
北千島の最北端。島全体が山で、聳える2,339mのアライド山は、北海道の旭岳よりも高い千島列島の最高峰。コニーデ型の山容は美しい。またアトラソワ島はドドの生息地としても知られている。 - シュムシュ島

1893年(明治26年)日本人開拓団が初めてその足跡を印した島。かつて国境の島として最果ての本土防衛隊があり、近くは北洋漁業の栄枯盛衰を見つめてきた島として日本の近代~現代史の舞台となった。アリューシャン列島のアッツ、キスカをアメリカ軍に奪われた旧日本軍は本土防衛ラインを北千島とし、その最前線がシュムシュ島だった。昭和20年には2万人が駐屯していたとされる。ポツダム宣言受諾直後にロパノカ岬から突然砲撃が開始され、旧竹田浜にソビエト軍が上陸した時、シュムシュは運命の島となった。そのままに放置されている戦車や大砲が当時の惨劇を伝える。93年には厚生省による遺骨調査団が初めて入ったが、半世紀前の重い記憶をあがなう作業は困難を極めている。 - パラムシル島

千島アイヌがポロモシリ「大きい島」と呼んだ北千島で最大、全千島でも択捉島に次いで二番目に大きい。北部にある人口約4,200人のセベロクリリスクは、北千島で唯一とも言える漁業の町。シュムシュからケトイ島に至る17の島々の北クリル行政区の中核。94年に根室市と姉妹都市提携を結び、水産資源の開発に力を入れている。日ロ合弁の水産加工場があり、カニなどが日本の食卓にも運ばれている。パラムシル島の北西沖に浮かぶプティチイ群島は近年のロシアの手厚い保護政策もあって、かつて日本も含めて乱獲していたラッコの楽園として復活しつつある。昭和初期からサケ、マス、タラ、クジラなどの漁業基地として栄え、漁期には1万人以上の漁民が北海道や東北地方から集まった。南西部は秀峰チクラチキを主峰とする2千メートル近い山岳地帯で、そのほとんどが活火山である。 - アンツィフェロワ島
パラムシル島の南西沖約10キロに浮かぶ周囲15キロたらずの海獣と海鳥の一大繁殖地。トドのハーレムや北海道ではほとんど見なくなってしまったエトピリカの大繁殖地として知られている。 - オネコタン島

千島全体でもクナシリに次いで2番目に大きな島。最近まで国境警備隊の他、防空レーター基地などが置かれていたが次々と撤退している。主峰のクレツィニナヤは火山学の教科書に必ず出てくる典型的な二重火山として知られる。リング状の火山湖は最大差し渡しが8kmという巨大なものである。 - ロブーシキ岩礁
世界的なトド、そしてキタオットセイの集団繁殖地として知られる。その数はゆうに1万頭を超える。ロブーシキンとはロシア語で「罠」の意で、潮流の難所でもある。 早春と夏の二度にわたっての撮影に成功した。 - ウシシル島

千島アイヌが「神が創った島」と名付けた千島一の奇観に満ちた島。雷神カンナカムイの住みかとされ、畏敬の対象となった。島は北島と南島に分かれているが、干潮時には歩いて渡れる。周囲は浸食の進んだ奇岩が多く、その風景は現実離れさえしている。い。内湾となるクラテルナヤ湾の海底からは現在でも盛んに火山性のガスが吹き出している。また島を取り巻く断崖全体が海鳥の営巣地となっており、北島から約1km離れたバブーシュカ島は北海道ではほとんど見ることが出来なくなってしまったエトピリカやウミガラス(オロロン鳥)など数百万羽が一大コロニーを形成している。 - シムシル島

ウルップ島に次いで中部千島で二番目に大きい。戦前は毛皮生産のためキツネとトナカイが飼育されていた。またクジラの処理工場も置かれていた。南端に国境警備隊の基地がある。 - チルポイ島
ブラット・チルポイ島と並んで「黒い兄弟」と呼ばれる男性的な景観の島。特にチルポイは別名「花の浮き島」と言われるほど海岸線から主峰チョールノゴ火山の中腹まで高山植物に満ちている。現在最も火山活動が盛んな山であり、戦前は日本が軍用として硫黄を採掘していた。 - ウルップ島
サンフランシスコ条約締結で日本は千島列島を放棄したが、どの島からを千島とするか日ロ国境を定めた日露通商条約の訳文で対立したいわくの島。日本は千島とはウルップから以北を指し、北方四島は入らないと主張したが国際的に認められなかった。そのウルップは海獣保護区に指定されている「ラッコの島」。冷戦の終了で軍備縮小の波が千島列島を洗う中、かろうじてレーダー基地が残されているが、物資の支給が滞りがちで隊員たちは自給自足を強いられてている。