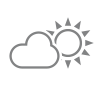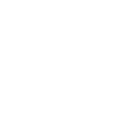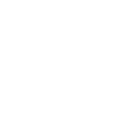NEXT
17:55
ウェザータイム
21:54
ウェザータイム
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~人気YouTuberとマシマシ夏キャンプin三重~
26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
東京オズワルドランド 水天宮前で番組ファンに遭遇!畠中破局の真相も明らかに
27:10
健康家族テレショップ
27:40
イイものショッピングゥ~!
04:10
朝までN天
04:19
オープニング
04:20
ダイレクトテレショップ
04:50
イイものショッピングゥ~!
05:20
筋肉元気!骨元気!100歳まで歩く秘訣とは?
10:00字
題名のない音楽会「名指揮者の考察!ボレロはなぜ繰り返すのか?を探る音楽会」
10:30
映画クレヨンしんちゃん新作公開記念 目覚めよ!インドパワー!みんなで踊れ!SP
13:55字
世界水泳シンガポール 今夜最終日SP~水泳ニッポン 新時代への系譜~
15:20
アナちゃん
16:25
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号! 北海道でいま注目の絶品グルメを紹介!
大樽通信
8月27日(水) 今の時代
先ごろ、社内報に書いた文章ですが、ここに転載させてもらうことにします。
これもプロデューサーとしての私の想いなのです。
「大切なものはなんですか」
今の時代、ドラマのテーマとしては、「コーラス」も「主婦」も、世間の耳目を集める題材としては地味なものでしょう。
でも、半世紀近く生きた私には、人生はどこまでいっても地味な出来事の繰り返しに思えてならないのです。
それでも、日本人は地味なものを歓迎しない風潮のまま数十年を過ごしてきました。
でも、本当に地味なテーマは、今を生きる人々に歓迎されないものなのでしょうか。
仮に、このドラマを観た人が、家を守り家族を養いながらスポットライトの当たらぬ家庭という地味な場所で日を送る主婦たちの歌声に感動させられてしまうならば、人々はけして地味なものを疎ましく思っていたわけではなかったのだということに気づくことになりはしないでしょうか。そしてその時、テレビは、今を生きる人々に、本当に大切なものはなんですかと問いかけることに成功する。
「本当に大切なものはなんですか?」
その素朴な質問を繰り返すことこそが、テレビドラマ本来の役割だったように、今、私には思えるのです。
ドラマ「歓喜の歌」の制作に着手する時、私の頭の中には、映画「フラガール」の印象がありました。
あの映画も閉山に追い込まれた炭鉱町が起死回生を懸けるべく、常磐ハワイアンセンターという娯楽施設を作り上げ、炭鉱町の娘たちにフラダンスを教え込み、そこの踊り子にするという「地味なテーマ」を中心に据えた映画でしたが、ラストは地味だと思っていたフラの踊りだけで15分近くを盛り上げ、それはそれは感動的なシーンに仕上げていました。
「私はあんたたちと出会えたことを誇りに思うよ」
ラストシーン近く、本番前の楽屋で松雪泰子さん扮するフラのコーチが炭鉱娘たちに檄を飛ばすシーンがありました。そのセリフを聞いて踊り子全員がひとつになる。そういう芝居場でしたが、その時、松雪さんのセリフを聞いて本気で泣いてしまっていた役者さんがいました。その人はセリフもないような端役の人でしたが、私はその人の涙に泣かされたのです。この現場には演技以上の何かがある。そう思ったのです。
フラの踊りは難しいと聞きます。きっと役者全員が立派に踊れるようになるまでには猛烈な練習を繰り返してきた日々があったのではないか。その辛かった日々が今報われようとしている。その思いが演じる役者の身に現実となって降りかかっていたのかもしれない。だからフィクションのセリフが、現実の自分に向けられたねぎらいの言葉に聞こえ、彼女は本気で感激して泣いてしまった。そんな気がしました。
だからこのドラマ「歓喜の歌」に二つの女声コーラスチームのおかあさん方が合唱協力してくださることに決まった時、出来る事なら彼女たちと一体感を築きたい。
私はそう思ったのです。
そして撮影までの半年間、私は週に一度ある彼女たちの練習日に顔を出すことにしました。
しかし一体感を築くための方策など最後まで思いもつかず、結局私はただ毎週毎週彼女たちの練習日に顔を出すだけの暇な男に過ぎなかったと思います。
それでも、練習日には必ずテレビ局の男が来ている。
何をするわけでも言うわけでもないけれど、目の前に座って聞いている。
そのことは、自分たちの練習時間を削ってドラマで歌う曲の練習をしなければならないおかあさん方にとって、忙しい家事やパート仕事の合間、週に一度、合わない都合を皆で合わせて作った練習日に、一円の出演料をもらうわけでもないのに、テレビのために普段は歌わない曲や、一度も歌ったことのない「第九の合唱曲」も暗譜しなければならず、ドイツ語の歌詞だって覚えなければならないおかあさん方にとって、いったい何のために自分たちは毎週毎週こんな余計な負担を抱えなければならないのだと仮にその中の誰かが思ってしまった時、目の前にテレビ局の男が座って聞いているならば、そうか、自分たちはとりあえずこの男のために歌っているのかと思ってもらえるかもしれない。
そう信じて私は毎週練習場所に通い、撮影の日まで、彼女たちのドラマへのテンションを持続させたまま引っ張り続ける道標の役割くらいは果たしてきたのかもしれないなと思うのです。
ドラマの要である脚本家の選定やキャスティングは、全て四宮氏がこれまでのドラマに懸けてきた7年間の経験と信用に裏打ちされた四宮氏の手腕ですから、もとより私などの力の及ぶところではありません。
ただ、私には、半年もコーラスのおかあさん方とお付き合いをして、理屈ではなく肌で感じることがあるのです。
それは、誰一人として暇をもてあまして合唱を始めるような人は居ないということでした。
誰もが家事やパートに忙しく、とくにバブル経済が崩壊してからは専業主婦で居られなくなる人が続出し、ほとんどの人がやむなくパート仕事を始めることになり、彼女たちの家庭はゆとりをなくしていくのです。
子供の手が離れたといっても今度は大学受験を控えたり就職を控えたりと気を揉むことが多くなり、その上に、高齢になった親御さんを抱えた人はそんな御両親の面倒を見なければならず、忙しさは減るどころか、むしろ増えるばかり。
でも、それが現実だということをあの人たちは知るのです。
だから朝六時に起きても夜寝るのは夜中の十二時、深夜一時。
そんなハードな仕事量を日々抱えながら、あの人たちは、どうしてわざわざコーラスなんかやるのか。
当初、私の中にあったそんな疑問も、半年間お付き合いするうちに、きついからこそやるのだということが分かる。
他人に使われるばかり、介護するばかりではとてもじゃないが人生など、やってはいられないのです。
でも、辛いからといって全てを放棄して逃げて行ける場所など、人生の何処にもないということをあの人たちは知っている。
そのことに気づけば人は自分のために好きなことをする。
そうしてあの人たちは合唱を始めた。
週に一度でも、皆で集まれる合唱の時間があれば息がつけるから。
人は自分だけの時間が手に入って初めて息を吹き返すことが出来るのです。
そしてその時間にだけ本来の自分に戻れる。
その時ばかりは、子供の面倒も、親の介護も、パート仕事も、家のことも何もかも忘れてコーラスに集中して好いのです。
指揮の先生に怒られることがあったって中学の頃の娘時代に戻ったような気がして嬉しくなる。そうやって、あの人たちは主婦という地味な持ち場に踏みとどまり、家を守り、家族を養っていくために、週に一度の練習を楽しみに通ってくる。
合唱は、あのおかあさん達にとって単なる趣味などといえるようなものではなく、自分の人生を乗り切るためのもっと切実な行為だったのです。
このドラマ「歓喜の歌」に登場するおかあさん達も、自分の力ではどうにもならない重石を背負わされながら、しかし逃げ出さず、自分の人生の持ち場に踏みとどまり続けます。
ラストの第九の合唱を聴きながら、観る者が感動してしまうのは、それが人生の重石を跳ね返す瞬間だからかもしれません。
人は背負わされた重石を跳ね返す瞬間に光り輝くのかも知れない。
だから与えられた重石を放棄していては、人は光ることもまた出来ない。
ドラマ「歓喜の歌」は、田中裕子さんや大滝秀治さんら名優の演技を通してそのことを思い出させてくれる現代の物語に仕上がっていると思います。
そしてこの物語を観終わる頃、ぼくらは不意にリアルなおかあさんたち自身の表情に遭遇し、やっぱりこのドラマは、協力してくれた、この人たちのドラマだったんだと素直に実感し、ぼくらは改めて胸打たれることになるのです。
本当に大切なもの。
一体それは何なのでしょう。
あなたには、その問い掛けが聞こえてくるでしょうか。