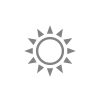TOP > HTBについて - 番組審議会だより
番組審議会だより
北海道テレビ放送では、番組審議会委員10名の方による放送番組審議会を設け、毎月1回(8月と12月を除く)審議会を開催して、放送番組の内容をはじめ、放送に関する全般的な問題についてご意見を伺い、番組制作の参考にさせていただいております。
番組審議会でのご意見は,2ヶ月に一度第4日曜午前5:35から放送の「あなたとHTB」でもご紹介していますのでどうぞご覧ください。
第506回北海道テレビ放送番組審議会概要
日時
2018年7月26日(木)
15:00~16:50
審議テーマ
「地上波テレビが生き残るために~インターネット社会の中で~」
出席委員
| 平本健太 | 委員長 |
| 斎藤 歩 | 副委員長 |
| 鳥居マグロンヌ | 委員 |
| 深江園子 | 委員 |
| 稲井良介 | 委員 |
| 高橋多華夫 | 委員 |
| 佐賀のり子 | 委員 |
| 嶋田知紗 | 委員 |
| 佐藤 敦 | 委員 |
会社側出席者
| 代表取締役社長 | 樋泉 実 |
| 取締役 | 森山二朗 |
| 役員待遇コンテンツ事業室長 | 川筋雅文 |
| 報道情報局長 | 大羅富士夫 |
| CSR広報室長 | 岡 仁子 |
| クロスメディアコミュニケーションセンター長 | 高田健司 |
| 番組審議会事務局長 | 斎藤 龍 |
【会社報告】
- 「水曜どうでしょうキャラバン」開催中
- 「てっし名寄まつり×出張HTBイチオシ!まつり」7/29(日)名寄市で開催
- 「北海道150年記念式典」8/11放送
【審議テーマについての委員意見要旨】
≪議題の前提≫
▼テーマ設定自体に違和感がある。「優位性を持っている」という過信や、「脅かされる」という言葉からもある種の錯覚を感じる。旧来のテレビ局という枠組みを維持することが前提の議論から一旦離れることも必要と感じた。
▼地方の地上波テレビ局には、視聴エリアが限定されるという制約がある。一方で限定された対象者のための情報サービスに注力できるということであり、そこに優位性がある。地域性の情報というものに関する視聴者のニーズは、ますます大きくなるのではないか。
▼インターネットが流す情報は、量が非常に多く、一々その信ぴょう性を確認するのが無理に近い。信ぴょう性のある情報、身近な情報、災害の時の情報などでは、テレビは負けていない。
≪視聴者が求めるもの≫
▼オリンピックやサッカーのワールドカップのようなテレビでしかできない臨場感、一体感は必要だ。東日本大震災の時のように非常時におけるテレビの存在はなくてはならないものだ。
▼スマホひとつあれば、調べられるものではない独自の視点取材が魅力となる。毒が強めでも、個性のある、主張のある番組、挑戦的な番組も個人的には見たい。
▼視聴者は共感できるパーソナリティを求めているのではないか。内容の良し悪しよりも、それを伝える人の好き嫌いで情報を選んでいると感じる。
▼インターネットやCS放送は自分で番組を選ばなければならないが、テレビはプロが選んで届けてくれるという点が、最大の魅力であり、責任でもある。受け身でいられるメディアがテレビの魅力だ。
▼自分の身近な情報を、しかも受動的に得ることが重要だ。この情報は、インターネットを見ていても接することがなく、能動的に得ようとする情報ではない。そういう意味では、より地域性の高い情報の発信が不可欠だ。
▼軸足を定めた継続的な取材に基づく番組を提供することが、地上波テレビに求められていることのひとつだ。インパクトや一過性の刺激だけを重視するユーチューバーによるコンテンツには望むべくもない、地上波ならではコンテンツだ。
≪公的役割≫
▼公共的な役割としては、やはり災害時の情報や対応。より早く、正確でまとまった情報が得られる媒体として重要だ。
▼テレビの圧倒的な影響力、信頼感からすると教育に役立てることが一番良いのではないか。地域格差を埋めるような教育、チャンスが与えられるようなきっかけになれば良い。
≪価値向上の論点≫
【信頼性】▼フェイクニュースやオルタナティブファクトとかいったものがまかり通る時代だからこそ、テレビには、情報の内容を精査し、信頼に値するものを選別して、わかりやすく提示してほしい。そうした役割がかつてないほど求められている。
▼インターネットにはないテレビの特徴は、社会に対して責任ある情報や、娯楽の在り方を提示できること。これまで築いてきた信用と責任が備わっているメディアであることは言うまでもない。
▼HTBは、「ひろばづくり」をひとつのキーワードに、テレビ媒体による接触体験のみならず、リアルな場における接触体験も含めて、共感を通じた信頼の獲得に努めているという点で先進的だ。
【ローカルの特性を生かす】
▼他の地域がうらやむ地域を、圏域放送が地域に暮らす人たちと一緒に創造することが必要だ。地域との濃密な関係を築くことができるサイズと形を目指したら、もっと独特の形になるはずだ。
▼正確で役に立つ地域の情報を真に発信できるのは地域の地上波テレビ局であるという意味で、ローカル局の存在意義が高まっていくのがこれからの時代だ。
【その他の論点】
▼あの人が作った番組、あの記者のリポートなら見てみたい、聞いてみたいと視聴者に思われるもの、テレビから距離を置き始めている若者にもそう思ってもらえるようなものをどれだけ生み出せるかが勝負と考える。
▼データの中で特に気になったのが、ティーンのテレビ離れだ。日本では、バラエティ番組は色々な年齢層のために作られ、ニュース番組やドラマは大人向け。逆にアニメは、小学生向けのものがほとんどで、結局どの番組もティーンが満足できるような内容がない。独特の年齢層として把握し、番組作りに取り組む必要があるのではないか。
▼動画チャンネルが人気なのは、自分が参加でき、双方向で交流ができることが大きい。一般の視聴者が、もっとテレビに出られるしくみがあっても良いと思う。
▼去年の統計では、道内3万1千人の外国人がいて、そのうち1万2千人が札幌に住んでいる。日本語の出来る外国人も、出来ない人もいるので、外国語が通じる病院や通訳者の連絡先など、日常生活の色々な情報を何カ国語かで伝えれば良い。
▼スマホを片手にTV視聴が当たり前の今、もう「ネット利用」の視点は間に合っている。むしろネットを使えない人や使えない環境にいる人への配慮は、多様な人に向ける視点として常に少しだけ必要だ。
▼世界中の人たちから信用されることを目指すより、地域に暮らす人たちから信用され、地域に対して責任を果たすことを目指すべきではないか。
▼マスがもはや一枚岩的なマスではない可能性が高い今日、視聴者の属性を従来以上に科学的かつ精緻に掘り下げて、番組のターゲット層を同定し、そこに訴求するような番組作りの重要性が以前とは比べものにならないほど高まっている。
≪HTBへの提言≫
▼信頼性がないメディアは、取捨選択されていく。ぜひHTBは、信頼のある生き残れるメディアであってほしい。
▼HTBはこれまで、「水曜どうでしょう」でのコンテンツ育成やアジアへのコンテンツ配信など、特色のある地域におけるビジネスモデルをいくつか確立している。豊平区で培った、地域と連携するという姿勢が、中央区に移った後、どのように変化するのか。今後どのような取り組みを行って行くのか、注目して行きたい。
▼この先にあるのは、同一地域内あるいは地域を越えた、そして同一系列内あるは系列を超えたアライアンスであり、力のある局を中心としたアンブレラ方式によるネットワークの再編が行われる可能性がある。そういう将来を見据えて、HTBには、取材力、番組制作力、地域の視聴が欲しいものを先取りして見出していく情報探索力などをますます充実させて欲しい。
次回の放送番組審議会は9月27(木)開催予定です。