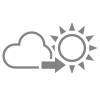TOP > HTBについて - 番組審議会だより
番組審議会だより
北海道テレビ放送では、番組審議会委員8名の方による放送番組審議会を設け、毎月1回(8月と12月を除く)審議会を開催して、放送番組の内容をはじめ、放送に関する全般的な問題についてご意見を伺い、番組制作の参考にさせていただいております。
番組審議会でのご意見は、2ヶ月に一度第4日曜午前5:40から放送の「あなたとHTB」でもご紹介していますのでどうぞご覧ください。
第556回北海道テレビ放送番組審議会概要
日時
2023年7月28日(木)15:00~16:30
審議テーマ
いま、テレビの役割を問う ~地域に貢献するメディアであり続けるために~
出席委員
| 岡田美弥子 | 委員長 |
| 斎藤 歩 | 副委員長 |
| 桜木紫乃 | 委員 |
| 及川華恵 | 委員(レポート参加) |
| 鍋島芳弘 | 委員(レポート参加) |
| 田村ジャニーン | 委員(レポート参加) |
| 樋口 太 | 委員 |
| 横田 伸一 | 委員 |
会社側出席者
| 代表取締役社長 | 寺内達郎 |
| 取締役 | 佐古浩敏 |
| 報道情報局長 | 伊藤伸太郎 |
| 編成局長 | 戸島龍太郎 |
| 編成部長 | 野沢和寿 |
| 報道部長 | 後藤雄也 |
| 社会情報部長 | 堀川 強 |
| ネットデジタル事業部長 | 田中和明 |
| 番組審議会事務局長 | 渡辺 学 |
| 番組審議会事務局 | 吉田みどり |
【審議テーマについての委員意見要旨】
≪地域の情報発信について≫
・「イチモニ!」や「イチオシ!!」をみても、出演者は視聴者にとって身近な存在で、地元のニュースや情報を共感して見ている。地方局は、視聴者にとって身近な存在、ほっとさせてくれる存在である、ということが大きな役割なのではないか。
・地域社会はいま、人口減少、経済の縮小、それに伴って起きるコミュニティ内のトラブルといった課題を抱えている。メディアに対しては、情報伝達にとどまらない、地域プロデュースや住民の暮らしのサポートといった新たな役割が期待されている。
・北海道の人は北海道の人が好き、という言葉をよく聞く。北海道にはプロの伝え手がたくさんいる。ネットに素人があふれている今だからこそ、地上波テレビには常に地元のプロが出ていてほしい。技術で情報を届けられる彼らの語彙力を信じ、テレビのファンを増やしてほしい。
≪非常時の情報提供について≫
・地域住民の生命や身体に直結する情報もあり、中立性・公平性が確保されているテレビこそが果たす役割は大きい。胆振東部地震では、インターネット、SNSで情報が錯綜した。だからこそ、冷静に、正確な情報を発信するという役割が求められている。
・外国人に向けた情報提供の方法を改善してほしい。インフォグラフィックなどのツールを上手く利用し、短時間で大量の情報共有を可能にすべき。さらに多言語の情報が見えるリンクの二次元コードを共有すれば、外国人が簡単に情報を得られる。
・災害時以外はあまり使われない日本語は、外国人にとって混乱を引き起こしかねない。例えば「ふつう」という言葉。過去に「電車は『普通』に動いている」と思い込んだ外国人が駅に行ったところ、『不通』だったことがある」という話を聞いた。災害時には命にかかわる事態にもなりかねない。
・災害時は、情報の正確性、迅速性、確実性が必要になってくる。こうした時に市民に安心して利用していただくためには、平時から発せられる情報の信頼性を勝ち取っていくことが必要。
≪ネットとの関わりについて≫
・マスメディア発信の情報と個人発信の情報がボーダレスになり、さらにコロナ禍の社会の停滞が通信によるコミュニケーションを加速させ、ネットとは一線を置いていた人々のハードルを下げたと感じる。そんな中でテレビをはじめとするメディアがそれらとどう共存していくか、むしろそれらをどう食っていくのかが求められているのが現状。
・「情報の信頼性」「情報の迅速性」「情報の公平性」「地域に根差した情報」「取材の継続性」以上の5点が、インターネットやSNSには足りないことであり、テレビならできることだと思う。テレビは、多くの人や時間やコストをかけて視聴者に情報を提供するメディアであることで、他のメディアとの差別化を実現できるはず。質の高い情報を提供することがテレビの役割ではないか。
・公共の電波で伝える情報は、自由なネットの世界に比べ、一定の枠、規制がある。それをプラスにとらえ、粗製濫造ではなく、良質な情報を届けるのだという意識を大事にしてほしい。
・テレビ受像機で視聴する人は減少しているはずなので、スマホやタブレット、パソコンでテレビを観る視聴者にとって、どのデバイスでも情報が受け取れるように技術を磨いていくことも必要。多様なデバイスに対応できるコンテンツそのものの制作も見直していかなければならない。
・ネット配信では、時間制約もそれほどなく、深掘りすることも、リラックスした雰囲気の緩さも含めた緩急のある番組制作の余地があると思う。テレビ放送枠の番組をダイジェスト版と考えて、より詳細な情報を欲しい方には可能な限り入手できるような環境づくりもあってよい。
≪その他≫
・多様な「自社コンテンツ」を抱え持つことが、ローカル局に必要。「コンテンツの地産地消」が地域にもたらす効果をもっと積極的に発信し、市民にその意味を認識してもらい、情報と人材がそこに集まる仕組みがあれば資金も集まる。その資金やミッションのサイズに適したテレビ局という会社のサイズや色と形が、自ずと現れるのではないか。
・ネットワークの拡大や充実を図ってほしい。具体的には、系列キー局や他の系列局との連携、動画配信サービス企業との連携、その他の関連するプレーヤーとのとの連携。それぞれのプレーヤーがもつ強みと弱みを補完し合いながら、コンテンツの多重利用を進めていってほしい。
・毎日の報道や情報は、自社のホームページや動画サイトなどで見ることができるが、その元となる素材は膨大であるはず。こうした素材を視聴できる取り組みもすべき。取材成果を公開トークショーとして披露してはどうか。視聴者との距離を縮め、身近に感じてもらうことでの信頼感獲得にもつながると思う。
・地方局は、先行した取り組みをしている他の地域局との連携を進め、キー局は、地方局間のマッチング支援などのプラットホーム機能を担うことを期待する。地方局とキー局が連携することで、より効果的な地域支援が可能になると考える。
・資金提供を公から受けるのも一つのアイデアかもしれない。公共が担うべきサービスの一翼を、テレビ局が委託を受けるという視点も今後必要かもしれない。更に、北海道ならではのアカデミズムとの連携による地域産業への貢献にも期待している。
次回の放送番組審議会は9月28日(木)開催予定です。