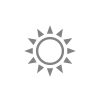TOP > HTBについて - 番組審議会だより
番組審議会だより
北海道テレビ放送では、番組審議会委員8名の方による放送番組審議会を設け、毎月1回(8月と12月を除く)審議会を開催して、放送番組の内容をはじめ、放送に関する全般的な問題についてご意見を伺い、番組制作の参考にさせていただいております。
番組審議会でのご意見は、2ヶ月に一度第4日曜午前5:40から放送の「あなたとHTB」でもご紹介していますのでどうぞご覧ください。
第555回北海道テレビ放送番組審議会概要
日時
2023年6月22日(木)15:00~17:00
審議テーマ
出席委員
| 岡田美弥子 | 委員長 |
| 斎藤 歩 | 副委員長 |
| 桜木紫乃 | 委員 |
| 及川華恵 | 委員 |
| 鍋島芳弘 | 委員(レポート参加) |
| 田村ジャニーン | 委員 |
| 樋口 太 | 委員 |
| 横田伸一 | 委員 |
会社側出席者
| 代表取締役社長 | 寺内達郎 |
| 取締役 | 佐古浩敏 |
| 報道情報局長 | 伊藤伸太郎 |
| 編成局長 | 戸島龍太郎 |
| 営業局長 | 橋本秀利 |
| 報道部長 | 後藤雄也 |
| 番組担当プロデューサー | 金子 陽 |
| 番組担当ディレクター | 本吉智彦 |
| 番組審議会事務局長 | 渡辺 学 |
| 番組審議会事務局 | 吉田みどり |
【審議対象番組についての委員意見要旨】
≪評価点≫
・この番組では、檀家の減少や後継者不足から宗教法人の売買や名義貸しが増加し、これに起因して深刻な問題が発生しているが、また有効な解決策を見いだせていないことを問題提起した。その社会的意義は大きいと思う。
・宗教法人の代表へのインタビューや彼の私生活等を追うにとどまらず、利用者、市民、納骨堂経営者、寺を売却した元住職ら、様々な立場の方への取材をし、御霊堂元町が開業してから破綻に至るまでの経緯、納骨堂の現状、実態等を伝えることで、本件の問題点は何なのかということをあらゆる視点から取り上げていたと思う。
・都市部で普及しつつある納骨堂の突然の閉鎖という事態を手厚く報じ、当事者の不安や怒りに寄り添う報道になった。問題の背景にある複雑さも含めて、全国に向けて発信するにふさわしいテーマだった。
・問題が発覚した当時の代表へのインタビュー、利用者たちの怒り、悲しみ、納骨堂の決算資料のコピーなど、生々しい材料がちりばめられ、迫力があった。
・落ち着いたナレーションと豊富な取材映像で、遺族の心情などが臨場感をもって伝わった。特に、住宅と車の賃料や実名入りの元住職のインタビュー、自宅の引っ越しの映像、函館取材からは、スタッフの並々ならぬ努力と気迫が感じられた。
・芦別市の寺の具体例を示し、墓じまいから納骨堂へのシフトが進んでいること、天候が要因となって北海道が全国の2割を占めていることに触れたのも親切だった。宗教法人格がネット上で売り買いされている情報も、その画面を見せることで「なるほど」と思わされた。
・冒頭の映像とナレーションは、暗く重いトーンで、この問題の根深い闇をよく表現できていた。それに続いて、御霊堂の経営破綻に関する説明があったが、納骨壇の使用料の金額や利用者の数など具体的な数字を使っていたし、利用者の悲痛な表情の映像をうまく重ね、この問題を詳しく知らない視聴者にとっても、わかりやすいものだったと思う。
≪要望点・改善点≫
・番組の内容がよくわからなかった。その理由として、情報の多くが視覚ではなく、聴覚を使って伝えるものが多かったから。同じテーマを扱った別の番組では、グラフやテロップを活用してわかりやすかったので、そうした工夫が必要だと感じた。
・今回の問題は複雑だったので、それぞれの出来事の時系列をはっきりすべきだった。いくつかのシーンには撮影時期が表示されていたが、小さいうえに表示時間も短く、わかりづらかった。
・音楽とテロップが仰々しく、くどかった。素材が強いのだから、サスペンスドラマ風の音楽、音響は必要ない。「納骨堂破綻」のタイトル文字も、夏の怪談番組みたいだった。
・納骨堂は、社会にニーズがあるからビジネスとして成り立っている。この番組は、このような法人の設立を容認している社会の構造を問う番組になっていただろうか。「問題提起」をするのだとすればそれが必要なのではないか。
≪提言≫
・番組を視聴して、納骨堂の経営が北海道という土地からまず崩れていったことには、なにかしら意味があるのではないかと思っている。今後は全国で同じような問題が起きると予感していて、もっとこうした問題について取り組んでいってほしい。
・30分という短い時間の中でトピックを絞り、それに肉付けしていく情報を整理すれば、視聴者に伝わりやすい番組になったと感じた。この問題は社会的にも関心が高いはずなので、引き続き取材を重ね、次回は放送時間を長くして問題の真相に迫って欲しい。
次回の放送番組審議会は7月28日(金)開催予定です。