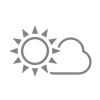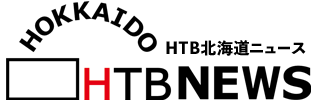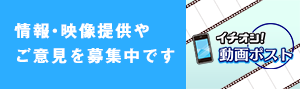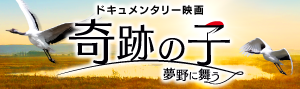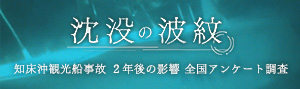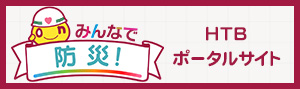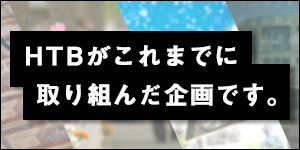「ピンク髪のツインテール…」指示繰り返し油絵制作に 道庁やビジネスでも 北海道内で広がる生成AIの活用
2025年 4月29日 12:44 掲載
札幌市中央区のアトリエに飾られた1枚の油絵。
蒼く描かれたふたりの少女が赤い目でこちらを見つめています。
実はこの作品…。
■PesMasさん:
「この部分の背景から、女の子はもう全部AI生成で、あとは色味とかを調節して、それ(AIで生成した絵)をタブレットで見ながらやっています」
この油絵を制作した札幌のアーティストPesMasさん。
PesMasさんが下絵の制作に使っているのが生成AIです。
生成AIは、人間の指示を受け膨大なデータをもとに文章やイラストなどを作り出します。PesMasさんが使用しているのはアメリカの企業が開発した生成AI「NovelAI」…画像や物語の生成に特化しています。
ひとつの指示で膨大なパターンの絵をつくりだすことができる生成AIで、PesMasさんは納得する絵が出てくるまで指示と生成を繰り返します。
■PesMasさん:
「今回は『ピンク髪のツインテールの女の子で、背景をネオンっぽい感じのバーみたいな感じ』という指示。この絵がいいっていう人もいると思いますし、さっき出したこういうのがいいっていう人もいるので、そこはやっぱ人間の感情の部分にもなってくるので、だからやっぱりクリエイターがこれをいいと思うか、これをいいと思うかっていうそのさじ加減でだいぶ変わってくる。こういう絵がポンって出てきた時に、俺より上手いじゃないかってなってがっかりってよりかは、『おお!!やった!!なんかまたなんかうまい絵ができたぞ!』みたいな感じで喜ばしい部分もあったりしますね」
納得した絵が生成されるとそれをもとに油絵を制作していきます。このようにして出来上がった数々の油絵作品。
しかし、ここで疑問が。
これらの作品づくりは、どこからどこまでが人間の「創作」といえるのでしょうか?
■PesMasさん:
「僕はAIはいち道具としての見方なので結局道具だから、それを使う人間のやり方次第。1枚だけポンってやって出たやつを発表するというか、そのまま何も加工しないでやるのは創造性がないって言われるかもしれないけど僕がやったパターンだと何百枚も何千枚もある中でこれがいいって選んだんだから、そこに創作意欲と創造性はあると思います。」
PesMasさんは、全ての作品で生成AIを使用しているわけではありません。頭の中で浮かんだものは、そのまま自分の力だけで描きますが、自分が想像できないものを創作したいときには生成AIを使っています。
■PesMasさん:
「僕はもう人間を超してほしいっていうかAIが、もうとにかく僕は面白いものが見たいんですよね。可能なことならば人間を超えて、もうAIがどんどん面白いものを作っていく世の中になったらいいなって思います」
ここ数年ニュースや生活の中でたびたび耳にするようになった「生成AI」。
生成AIは、進化を続けています。
AIに文章や画像など様々なものを学習させ、人間の指示や質問に対して期待される答えが返ってくるよう訓練を行うことで、さらに高度な文章や画像が生成されるようになります。
2年ほど前にアメリカの企業OpenAIが対話型AI「ChatGPT」のサービスをインターネットで公開したことをきっかけに様々な生成AIが開発され、私たちの社会の中で急速に広がりました。
この技術はいまや質問ができるチャットサービスやネットの検索に使われるなどしていて、身近な存在となっています。
広がりは北海道庁にも。業務に生成AIを導入しました。
生成AI利用するにあたっての注意点などを学んだうえで、メールの作成や、議事録の要約、新しい企画のアイデアなどに活用しています。
札幌のベンチャー企業調和技研では、生成AIを使った様々なサービスを開発しています。
こちらは調和技研が開発したサービス「AIWEOforヘルプデスク」。ビジネスや社内に関する疑問や質問に答えてくれる生成AIです。
■調和技研研究開発部 高松一樹さん:
「人間しかできなかったけど比較的単調な仕事みたいなところが生成AIの方でも置き換えられるようになってきましたので、人間の方はその分、例えばお客様に対応する時間を増やせるですとか、そういう業務のシフトみたいなところがおきていくのかなと」
活用が広がる一方で、生成AIに仕事が奪われるのでは?という心配や生成AIが膨大なデータを利用して生み出したものは誰かの著作権を侵害しているのではないかという疑問の声もあります。
■北海道大学大学院情報科学研究院 川村秀憲教授:
「例えば日本はAIをトレーニングするためには、特に著作権があるものを使って構わないということになっている。(ただ)学習のところで問題がなくても、例えば著作権のあるデータそのものが出力されると、これは問題になりますよね」
北海道大学でAIの研究をしている川村秀憲教授。生成AIが誕生する以前から、俳句を詠む人工知能「AI一茶くん」を開発をするなどしてきました。
■川村秀憲教授:
「今の最新ChatGPTで画像を作るのにジブリ風に写真を変換するっていうことが、いま世界的にすごい流行っていますよね。これジブリ風っていうのはジブリそのものではないので、ジブリ風の作品っていうのは著作権に当然抵触しないものも多いとは思うんですけども、でも中には偶然ジブリが著作権を持っているキャラクターに近いものができることもあって、それが果たして著作権上アウトなのかセーフなのかっていうことのラインも非常に難しい問題ですよね」
権利の問題だけでなく、技術革新が先行する生成AIは、悪用されるさまざまなリスクをはらんでいます。
川村教授はそれでも生成AIの発展を止めるのではなく、生成AIによって起きた様々な問題に対してルールを話し合っていくべきだといいます。
■川村秀憲教授:
「我々がこの新しいテクノロジーを自分たちの社会の発展のため、我々の幸せのためにどう使っていくのかっていうことを考えて正しく使っていくことが大事じゃないかなと思います」