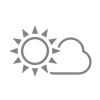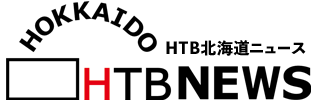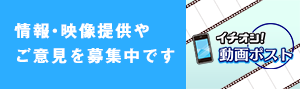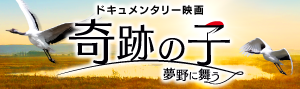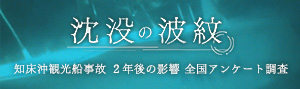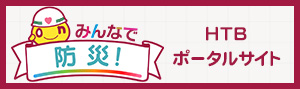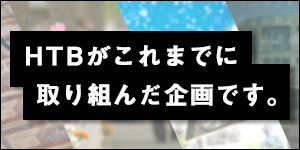北海道内で募集停止相次ぐ短期大学 人口減少と疲弊する地方…変わる時代のニーズに生き残り策は
2025年 5月 7日 17:59 掲載
肥沃な土壌に恵まれ、農業が盛んな深川市。
1966年に創立された拓殖大学北海道短期大学は市内唯一の大学です。
保育学科と農学ビジネス学科の2つの学科を持ち、授業のために敷地内におよそ4haの農場が用意されています。
■拓殖大学北海道短期大学山黒良寛学長:
「主に農業の後継者としてここで勉強するということで、それを目的とする学生が多いが、最近は農業に関連した産業、地域の産業を目指す人が多い」
農業の担い手や地元の保育士など、地域の即戦力となる人材をおよそ60年にわたって送り出してきましたが、大学は先月入学した32人の学生を最後に募集の停止を決めました。
■山黒学長:
「少子化や地方都市の人口減少や4年制大学の進学率の向上など、色々理由はあると思うが、やはりどの大学においても抱えている問題だと思う。
今回、学生募集の停止とと苦渋の判断をした」
道内では、去年、札幌市の北星学園大学の短期大学部が募集停止を発表。
さらには、先月、釧路市の釧路短期大学でも募集停止を発表しました。
文部科学省の調査によりますと、道内にはかつて22校の短期大学がありましたがこの20年で13校にまで減少。学生数も、およそ7000人減っています。大学の制度について詳しい専門家は女性の社会進出や、価値観の変化などが背景にあると指摘します。
■北海道大学教育学部光本滋教授:
「20年前、30年前は短大というのはどちらかというと女性が行く短期の高等教育機関だった。当時は一般職と言われていましたけど、地域採用的な枠があって、そこに短大卒の人が大勢就職していたと思うのですがそれがやっぱり小さくなっていったのと、女性の進学先も多様化していますよね。
4年制大学に進学する方も増えますから、やっぱりそういう意味で短大が選ばれにくくなっているのかなと思います」
若者の数が減っていることに加え、若い世代を中心に、進学や就職時に首都圏へ移動する「東京志向」も状況に拍車をかけます。
地域の担い手を育成してきた短期大学の閉校は、自治体にとっても、大きな影響が。
■深川市まち未来推進課高田祐貴課長:
「農業は後継者不足という面においては、地元の短期大学で勉強して農家に戻っていくかという形はこの先どうなるかというのかは不安になる/地元で育った人間以外にも、短期大学で関わった人々が深川市にまた来ていただけるような仕組みづくりがあるといいなと思っています」
地域に根ざした教育方針の中、大学が40年以上続けてきたミュージカルの公演は市民に親しまれてきたイベントでした。
■深川市民(30代):
「私卒業生です/卒業生として母校がなくなるのは寂しいですね」
■深川市民(60代):
「ミュージカルとかがあっただから良かったのでは/若い人がいなくなるのは寂しい」
■深川市民(30代):
「大学があることによって若い人たちが町に来る理由になっていた」
町とともに歩んできた柘植大学北海道短期大学。
最後の学生を送り出し、再来年春に閉校する予定です。
■山黒良寛学長:
「拓殖大学の建学の精神を忘れることなく/人を愛して地域を愛して地域を愛してもらえる人材として活躍してもらうこと/本学は残念ながら閉校になりますけど、その精神は卒業生がいる限りは生きているわけですから決してこの場をもって役割を終えるのではなく、卒業生がいる以上しっかりと担っていけるという風に考えています」
地域に密着した大学を維持しようと国の支援に活路を見出す動きも。
保育士や栄養士を目指す学生を養成する函館短期大学。
こちらも定員割れが続き、各学科の定員が110人に対し、学生数はおよそ80人にとどまっています。
■函館短期大学澤辺桃子学長:
「非常に厳しいです。一時期は定員が120ということで、倍いたときもありますから。どんどん減ってという状況で/定員を下げて、充足率を挙げていくという、それを4大、短大限らずどこの大学もしている状況かという風に思います。」
厳しい運営環境の中、手を挙げたのが今年から始まった文部科学省の経営改革支援です。少子化や18歳人口が減少する中、地域における専門的な人材の育成事業に対して、5年間、1千万~2千500万円の補助金を支給します。函館短期大学は道南という地域の特色を生かし、再生可能エネルギーが中心の社会に転換する「GX」の教育をアピール。
■澤辺桃子学長:
「実際に近くで風車を見に行くとか、あるいは地熱発電もありますので、そういったところを学生たちと勉強のために視察に行って、それを子供たちに伝える」
全国の111校が応募し、函館短期大学を含めた45校が選ばれました。
■澤辺桃子学長:
「首都圏の高校生なり、若者にアピールしていける材料なのかなと思っています」
全国の111校が応募し、函館短期大学を含めた45校が選ばれました。
■学生の発表:
「欠食気味の保護者へのアドバイスは、子供は親を見て成長するので、ちゃんと食べて欲しいと思いました」
この日は、保育学科に先月入学した1年生の「食育」の授業。
漁業などが盛んな道南だからこそ、食の大切さを教えられる保育士を養成し、地域の担い手不足にも貢献したいとしています。
■1年生:
「将来は、自分の通っていた幼稚園で働きたい」
「少子高齢化という面でも、自分が保育者になって一緒に(町を)活性化できたらと思ってここにいます」
■澤辺桃子学長:
「地域で必要だと言われているうちは、なんとかいろいろな形で補助金を申請したり、みなさんにご協力いただいて、維持していきたいと考えています。
どうしようもない字状況になってくるかもしれませんが、こればかりはわからないので、あるうちは、学生のために一生懸命本学教職員は頑張って教育をしていきたいと考えています」
時代と共に大きく変わりつつある短大へのニーズ。地域とどのように歩んでいくのか。
短大はいま、岐路に立たされています。