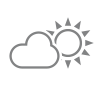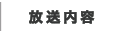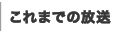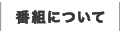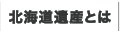NEXT
13:59字
ポツンと一軒家 豪快にイノシシ捕獲!離れて暮らす家族集まり笑顔で鉄板BBQ大会【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 政界はどう変わる?キーマンが生出演!
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 自然を守る?
17:55
ウェザータイム
22:04
ウェザータイム
24:10
探偵!ナイトスクープ 【熱き挑戦!】87歳の草野球選手は外野へヒットが打ちたい!
25:10
おぎやはぎのハピキャン ~新生活におススメ!最新アウトドア情報~
26:40
ウェザータイム
26:45
アナちゃん
26:50
東京オズワルドランド 【オダウエダ植田の健康診断で衝撃の数値!】
27:20
健康家族テレショップ
27:50
テレショップ
04:19
オープニング
04:20
ダイレクトテレショップ
04:50
まるっと健康これ1杯青汁の魅力 徹底解明
05:20
アナタもツヤめく美しいお肌へ
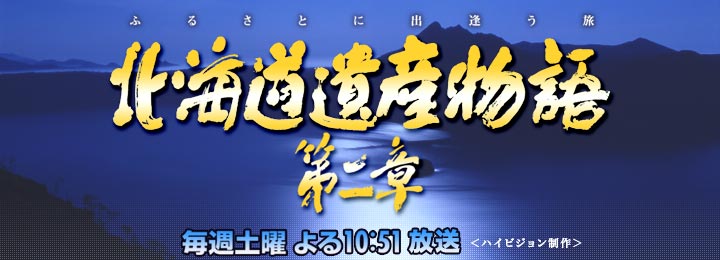

2007年9月8日放送

第20話「日本一のそばの里 ~幌加内町」
いまや、日本一のそば生産量を誇り、全国のそば店でも品質の良さで、高く評価される 幌加内町のそばは、全国でも知る人ぞ知る有名産地としての地位を確立するようになりました。しかし、それには雄大な自然と、そばに情熱をかける人たちと、20年以上にわたるそば栽培の歴史があったのです。
2007年9月1日放送

第19話「廃墟の歴史を磨く人・羽幌炭鉱」
石炭の町として栄えた羽幌。 昭和40年頃には、およそ3万人が暮らす賑やかな炭鉱町でした。 戦後復興の原動力となった炭鉱。 そこに生きた人々の足跡を辿りながら 朽ちた建物の中に新たな息吹を吹き込む人がいます。 「ヤマの記憶」を失うことは、町の歴史を消し去ること。 それを避けようと、自ら本やマップを準備し 自分自身が生まれ育ったまち。 廃墟と化した炭鉱で父母の想いを探します。 その土地を愛する想いこそが歴史を磨き、 忘れられた時間に輝きを与えています。
2007年8月25日放送

第18話「ぬくもりの学び舎・増毛小学校」
優しさが溢れる思い出の風景の中に町のシンボル。増毛小学校があります。 増毛小学校が建てられたのは昭和11年。現存する木造校舎として北海道で最も古い小学校です。 歴史薫る建物は、町の語り部。様々な時代を彷彿させるこの町には何世代にもわたって同じ学び舎の記憶を分かち合う人々がいます。 鉄路の途絶える町、増毛を訪ねます。
2007年8月18日放送

第17話「原始の森・太古の大地」
1500年前の北海道を知る大木。黄金山の麓に、森の主であるそのイチイの木は立っていました。
痩せて枯れたように見える幹の先で、空に向かって大きく背伸びする枝には青々とした葉が繁り、命の神秘を漂わせます。
樹齢800年という昭和の森のクリの木は、北の大地を流れ過ぎていった様々な時間をどんな思いで見つめてきたのでしょう。
森の賢者たちに出逢いに、原始の森を巡ります。
2007年8月11日放送

第16話「天才兄弟の心の故郷」
厚田にふく「あい風」とは、海を藍色に染める北西の風。
この町の一角にある「ルーラン」という地名が気に入り生まれ故郷を偽った天才画家、三岸好太郎には異父兄弟がいました。文豪、子母澤寛です。
晩年に藍色の海を描いた「海洋を渡る蝶」。そして「この村に老夫の墓でもあったなら」とつづった兄。二人のこころの故郷が今も変わらずここにあります。
この二人の天才を生んだ厚田村の原風景を探ります。
2007年8月4日放送

第15話「自然を哲学とした人・岡崎文吉」
暴れ川と呼ばれた石狩川。その川を制した人の哲学に触れます。
岡崎文吉。彼が治水工事で提唱していたのは自然主義。
自然から学び、必要以上に手を加えないというものでした。
今、再びその自然主義が脚光を浴びています。
2007年7月28日放送

第14話「水の都・小樽」
小樽はニシンや石炭の積出港として栄華を誇った町。
そして、特異な地形から流れ出す豊富な水が数多くの酒蔵を生みました。
華やかな時代を過ぎても酒蔵が消えなかったのは宝の水のおかげです。
小樽の街を潤す命の水の源流を辿ります。
語りは女優・中嶋朋子さんです。
2007年7月14日放送

第13話「いつか見た夏~忍路海岸」
明治41年、北大水産学部の前身として、忍路の浜に臨海実験所が設立されました。 忍路湾は大きく波立つことが少ないため、海洋生物の宝庫なのです。 100年を超え、今も北の漁業を支える施設として活動を続けています。 また、オタモイ海岸には昭和初期、一大リゾート基地が存在しました。 施設の一つ、「龍宮閣」は京都の清水寺を凌ぐといわれ、 毎日数千人の人々で賑わったそうです。 戦後すぐに焼失し、その面影はごく一部にしか残っていません。 当時の雄大なロマンの跡を探ります。
2007年7月7日放送

第12話「瀬棚に残る女性医師の足跡」
のどかな景色が広がる瀬棚町。
そこには高き理想を胸に神の教えを貫いた一人の女性の足跡が残っています。
「荻野吟子」。彼女は時代の偏見と戦いながら勉学に励み、
35歳にして日本の女性医師第1号の座を手にしました。13歳年下の青年牧師と結婚し、理想郷を築く夢を抱いて北海道に移住した吟子は、聖書を片手に、医師として人を救うことに愛を見出します。
海沿いの小さな町で、彼女の熱き思いのかけらに出会うと、誰もがその凛とした生き方に胸を打たれます。
2007年6月30日放送

第11話「郷土愛漂う街角」
江戸末期から昭和初期にかけてニシン漁で栄えた町、江差。今、その街並みが「いにしえ街道」として再現されています。
伝統を守り続ける町には、海の恵みで栄えた時代を今に伝える心熱き語り部たちが住んでいます。
その「100人の語り部」と呼ばれる人たちが伝えたいことは、再現された街並みや江差の歴史だけではなく、
そこに生きた人々の「町を愛する思い」でした。