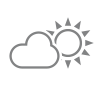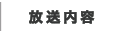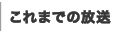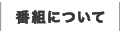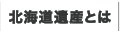NEXT
13:59字
ポツンと一軒家 豪快にイノシシ捕獲!離れて暮らす家族集まり笑顔で鉄板BBQ大会【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 政界はどう変わる?キーマンが生出演!
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 自然を守る?
17:55
ウェザータイム
22:04
ウェザータイム
24:10
探偵!ナイトスクープ 【熱き挑戦!】87歳の草野球選手は外野へヒットが打ちたい!
25:10
おぎやはぎのハピキャン ~新生活におススメ!最新アウトドア情報~
26:40
ウェザータイム
26:45
アナちゃん
26:50
東京オズワルドランド 【オダウエダ植田の健康診断で衝撃の数値!】
27:20
健康家族テレショップ
27:50
テレショップ
04:19
オープニング
04:20
ダイレクトテレショップ
04:50
まるっと健康これ1杯青汁の魅力 徹底解明
05:20
アナタもツヤめく美しいお肌へ
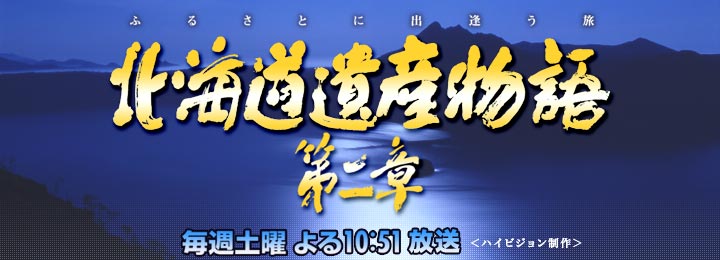

2007年11月17日放送

第30話 「水と大地が響き合う・羊蹄山麓~京極町」
ふなば農場の船場英雄さんは3代にわたり京極町で農家を営んでいます。
今年は80年ぶりという記録的な干ばつで、農作物の収穫が危ぶまれました。
船場さんらは羊蹄山麓に湧き出す伏流水を、家族総出でくみ上げ、3週間ものあいだ寝食を忘れ畑に水を撒いたといいます。
船場さんは、「食育」にも熱心に取り組み、地元の子供たちに大地と農業の本当の豊かさを教えています。
2007年11月10日放送

第29話「人生はばんばとともに ~岩内町」
岩内町にある田中牧場は、ばんばの育成牧場。
子供の頃から「馬」とともに暮らしてきた76歳の田中さんは、親の代から、馬車追いを生業にし、馬とともに岩内の産業を支えてきました。
『北海道開拓の立役者としての馬文化を消してはならない』と訴え、きょうも、岩内沿岸の砂浜の練習場で、300kgのソリを曳かせます。
ばんばにかける情熱は、帯広市の単独開催となった今でも衰えていません。
2007年11月3日放送

第28話「聖地探検・後篇/尻別川のアイヌ語地名」
今からおよそ150年前、この川を行く探検の旅に出た松浦武四郎は
聞き取ったアイヌ語で周辺の地名を詳細に書き入れ、その記録を1冊の本にまとめました。
坂の下り口を意味するルウサンを過ぎ、ワッカタサと呼ばれていた京極町を抜けクッシャニ、現在の倶知安町へ、今なら数時間で下れる行程を当時は数日間要したといいます。尻別川には「フイラ」と呼ばれる激流の難所が多く小さな丸木舟の行く手を何度も阻んだからでした。木の葉のように川面に激しく揺られながらそれでも武四郎がこの探検を放棄することはありませんでした。流れの静かな昆布川との合流地点に出た時、武四郎は、「夢のごとし…」と回想しています。
この地を知り尽くしたアイヌの人たちの知恵を借りながら、その探検を成功させたのです。
10日ほどかけた全行程の記録は、今も北海道の地名として残り、当時の様子を私たちに語りかけてくれるのです。
2007年10月27日放送

第27話「聖地探検・前篇/尻別川のアイヌ語地名」
自ら未開の原野に分け入りアイヌの人々の案内で
今からおよそ150年前に完成した北海道の地図。
このアイヌ語の地名を入れた詳細図を完成させたのは
松浦武四郎です。
彼はまた「後志羊蹄日誌」の中で
尻別川流域探検の様子を克明に綴っています。
今の数倍の水量があったであろう川を下ることは
探検家の血を高ぶらせたに違いありません。
幕末の探検家、松浦武四郎の川を行く旅は
神々しくそびえ立つ羊蹄山と尻別岳の二つの山に見送られるように
武四郎を乗せた丸木舟は今の喜茂別町を出航。
彼の壮大な夢が、未知なる原野に漕ぎ出しました。
2007年10月20日放送

第26話「鰊がもたらした心の回遊・後編~寿都町・御宿鰊御殿」
現在、この鰊御殿は、「御宿鰊御殿」として旅館営業しています。
女将は、橋本家3代目、橋本敏子さん84歳。
鰊漁栄えし頃の「語り部」です。
多くの人々に愛され続けた寿都は、鰊漁が衰退したあとも、黒松内~寿都に鉄道が開通し、寿都は「豊かな海の幸」を求めて、岸信介、佐藤栄作などの歴代総理、曽野綾子、角川源義ら文化人。そして力道山や立川談志など、多くの観光客が訪れたといいます。
橋本家3代目女将の「寿都の海」をこよなく愛する姿を描きます。
2007年10月13日放送

第25話「鰊がもたらした心の回遊・前編~寿都町・御宿鰊御殿」
この鰊御殿は、一般的な網元や漁師たちが寝泊りしていた建物ではなく、漁場で網元や漁師に品物や金を貸し、代金を数の子、身欠鰊、鰊粕等で返済し売る「仕込屋」として商売をしていた橋本家の建造物です。
建材を集めるのに3年、建築に4年の歳月をかけ明治12年に完成。
総工費は当時で7万円を要したというこの建物は、床下には防湿のため6百表もの木炭をしきつめ、窓は当時ギヤマンといわれたガラスをオランダから取寄せるなど、豪華な調度品をそろえ、鰊にわきたつ浜と海の商人の盛時を偲びます。
2007年10月6日放送

第24話「宗谷丘陵からの風・サステナビリティ・稚内市」
風に回る風車のように今私は大きく手を広げて宗谷丘陵に立っています。
美しいこの丘で出会った一組の夫婦。
夫婦が、広い鶏舎の中で飼育しているニワトリ。
エサにも特別なこだわりがあります。輸入飼料は一切使わず、地元産のものだけを使用。
地域がひとつになって次の世代へ遺していけるものを模索しようとする思いが伝わります。
持続可能なこと、「サステナビリティー」をベースに肩の力を抜いて活動すること。
そうすることで「食の安全」という言葉の響きから硬い殻が取れるのだと夫婦は信じています。
2007年9月29日放送

第23話「宝川の恵み・天塩川・後編」
天塩川に今起こっている異変とは?
サロベツ原野を大きく蛇行する日本有数の大河川、天塩川。
その支流の先にある小さな沼、パンケ沼へとやって来ました。
洪水防止の目的もあって
蛇行する流れに人の手を入れたことでサビが発生して赤く濁った水からは、自然の叫び声が聞こえてきます。
漁師達が「宝の川」と呼ぶ天塩川。
恵み豊かなその川は、遠い未来の北の大地へ今、警鐘を鳴らしているのかもしれません。
2007年9月22日放送

第22話「宝川の恵み・天塩川・前編」
豊かに水を湛えて滔々と流れる天塩川。
その恵みに触れる旅に出ました。
平野を蛇行しながら日本海へ注ぐ大河川、天塩川。
河口近くでは質と量ともに全道一を誇るシジミ漁が盛んです。
豊かな自然に恵まれた川を漁師は宝の川と呼びます。
川の恵みの豊かさを伝えるのは、ひと掻きの網の重さと、採れる貝の質です。
しかし、その天塩川に今異変が起こりつつあると言います。
2007年9月15日放送

第21話「光降り注ぐ星の里~初山別村」
月明かりにまぎれて、ひっそりと瞬きする小さな星たち。
そんな星たちに出会える初山別村に来ました。
みさき台公園の天文台で、間近に見る星の姿に胸が高鳴ります。
沢の葉陰に光るのは、ヘイケボタル。
初山別をホタルの里にしようと、毎年5千匹が放流されているといいます。
その幻想的な光の競演は、闇の中で膨らむイマジネーションの中でロマンを掻き立てます。