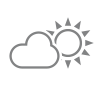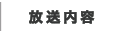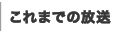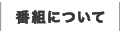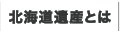04:15
テレビショッピング
NEXT
04:45
元気に歩き続けるための秘訣を大公開
05:15
イチおし!プレミアム
05:45
アナちゃん
13:59字
ポツンと一軒家 豪快にイノシシ捕獲!離れて暮らす家族集まり笑顔で鉄板BBQ大会【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 政界はどう変わる?キーマンが生出演!
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 自然を守る?
17:55
ウェザータイム
22:04
ウェザータイム
24:10
探偵!ナイトスクープ 【熱き挑戦!】87歳の草野球選手は外野へヒットが打ちたい!
25:10
おぎやはぎのハピキャン ~新生活におススメ!最新アウトドア情報~
26:40
ウェザータイム
26:45
アナちゃん
26:50
東京オズワルドランド 【オダウエダ植田の健康診断で衝撃の数値!】
27:20
健康家族テレショップ
27:50
テレショップ
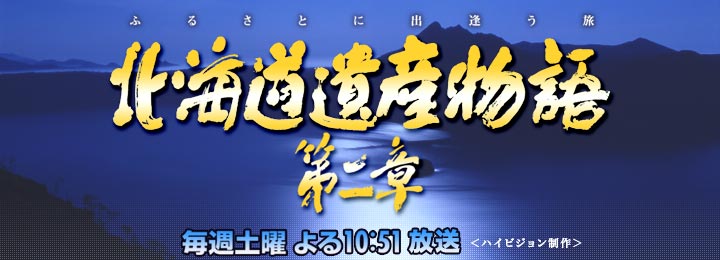

2008年2月2日放送

第40話「開拓使誕生物語5 ~もう一人の密出国者・中川清兵衛」
新潟県与板町。現在長岡市与板。ここで開拓使麦酒醸造所開設のもう一人のキーマンが誕生します。中川家の分家の長男に生まれ、本家を継ぐべく養育されましたが、家を出て横浜に行きドイツ商館のボーイとなったと言われています。
慶応元年、村橋らがイギリスに渡ったその年、17歳の少年中川清兵衛もまた密出国して渡英していました。幕末の混乱期に時を同じくして密出国を果たす二人。
その目的は近代日本を創りあげることに他ならなかったのです。
2008年1月26日放送

第39話「北を目指した薩摩人・開拓使誕生物語 4 ~ サッポロビール創始者・村橋久成」
北海道を代表するブランド サッポロビールを作り上げたのは卓越した行動力の人、村橋久成。
彼は、薩摩独特の郷中教育と仏教の教えを軸としたいろは歌でその志を磨いたと言われます。いろは歌で人としての道を学んだという薩摩の人たちは類まれなる行動力の持ち主でもありました。日本の将来を案じ鎖国政策中に海外に飛び出していった薩摩隼人達。
その中に村橋久成がいます。世界的視野をもって作られたサッポロビールは今も誇らしげに開拓使のシンボル、御陵星を掲げています。
2008年1月19日放送

第38話「北を目指した薩摩人・開拓使誕生物語3~薩摩魂の継承」
北の開拓を支えた魂 -開拓者魂-の原点を、ここ鹿児島で見つけました。
地元の人々が愛してやまない西郷隆盛。彼が遺した強靭な魂の遺産は、墓のある神社の境内で今でも子供たちの心を育てています。鹿児島で西郷隆盛像を見上げながら県民の中にある「西郷さん」の存在の大きさを実感しています。天を敬い、人を愛することを胸に刻んだ薩摩の巨星の志、薩摩魂とは、まず自らが実践することだと言います。
薩摩独特の攻撃的剣法、自顕流の伝授はその魂の継承です。
2008年1月12日放送

第37話「北を目指した薩摩人・開拓使誕生物語 2~ 国づくりへの挑戦」
開拓使のルーツを探る旅が桜島のそびえる町へと誘いました。
私が訪ねたのは、「集成館」と呼ばれる場所。日本を近代国家へと導いた工業施設群跡地です。かつてここに集まっていたさまざまな工場は島津斉彬が造らせたもの。鎖国政策を執る日本にあって、国内の産業技術向上に立ち上がったのが、自らが行動することを美徳とする薩摩の人たちでした。日の丸の発案者と言われる島津斉彬は世界に目を向け幕府や藩の中に生きる人々に初めて「国」という概念を説いたのです。
札幌創成川東岸の工業団地。あらゆる工場とそこに働く人々が、未来の日本を紡いでいたその場所は、正に「北の集成館」です。世界を見据えていた薩摩人は南と北を結ぶことで日本という国づくりに挑戦していたのです。
2008年1月5日放送

第36話「北を目指した薩摩人・開拓使誕生物語 1 ~ 薩摩の名君」
北海道のシンボル、道庁赤レンガ内に飾られた、歴代北海道首長の肖像画の明治の年号をたどると、その殆どが鹿児島人である訳を、薩摩の歴史が教えてくれました。
16世紀の世界地図に記された鹿児島の名。古くから海外との交流が盛んだったこの地で、幕末の名君 島津斉彬は日本の未来に思いを馳せていました。技術と実力を備えた西欧諸国から日本がいかに遅れをとっているかを説き幕府に対して積極的開国論を提唱し、勢力を拡大するロシアに対しては北方警護を目的として蝦夷地の開拓が必要であることも訴えました。世界につながる薩摩の海から北の未来をも案じていたのです。
赤レンガ正門からまっすぐ東に伸びる北三条通りは「開拓使通り」と呼ばれる北海道初の舗装道路。この道を歩いた先人達の志を探る時、遠い薩摩の地に、そのルーツを見出すのです。
2007年12月22日放送

第35話「甦る鰊魚場・古民家再生にかける匠の技~余市町」
鰊漁全盛期の建物が数多く残る後志沿岸には、番屋など御殿と呼ばれる建物を移転保存されるケースはありますが、漁夫の住いや網倉などの多くは取り壊されています。
余市に住む福井さんは、そんな漁場建築に愛情をもち、古くから使われてきた建築部材にも、新しい命を吹き込む「匠の大工」です。
太く、長尺な梁や柱、欄間などを近代建築に取り入れ、新築住宅の一部として再利用しています。「繁栄と歴史を重ねてきた材にとてつもない魅力を感じる」と匠は古材の魅力を伝えています。
2007年12月15日放送

第34話「寒風がつくる逸品・鮭の寒干し~寿都町」
風のまち、寿都の風を活用し、「鮭より美味い鮭」づくりに励む人がいます。
生食の鮭はノルウエー産の大西洋鮭や道東沖のシロ鮭が好まれているのを見て、「郷土である寿都の鮭をなんとかブランド化できないものか?」という想いで試行錯誤をかさね生まれたのが「寒干し」です。
寒干しの鮭は、雪をかぶることによって保湿効果が生まれ、身の乾燥がゆっくりと進み独特の旨みがでるといいます。
2007年12月8日放送

第33話「ブナ林からの警告・地球温暖化/黒松内町」
日本最北のブナの森で私は太古の風を感じています。
この森には大切な役割があるそうです。
日本の固有種であるブナが生息する最北の地は、渡島半島北部の黒松内町です。
この最北のブナの森は年々ゆっくりと確実に北へ進んでいます。
温暖化がこのまま進むと、100年後の日本には1割に満たないブナ林しか残らないという説もあります。
北進する森は、地球からの大切なメッセージに違いありません。
未来の子供たちへ何を遺したいのか?
その森に行くと、ふと立ち止まって誰もが考えてみたくなるのです。
2007年12月1日放送

第32話「ブナ林再生プロジェクト/黒松内町」
黒松内のブナ林で、この町で進む未来への取り組みの大きさを実感しました。
「ブナ林再生プロジェクト」。
このプロジェクトが目指すのは、一人、100平米のブナ林を作ること。
周りに生い茂るササの駆除法などに子供たちの真剣な眼差しが注がれます。
沢山の実を落とすのは5年に一度位というブナ。ちょうどその年にあたる今年、子供たちは木の下にネットを敷いて明日の森の種を集めていました。
ひとつひとつ大切に集めた実は、近くの荒れ地まで持って行きます。
そこが未来のブナの森。
それは、未来の地球と未来の子供たちへのかけがえのない贈り物です。
立派なブナ林ができるようにと期待で胸を一杯にしながら小さな手が大きな夢の種を植えていきます。
2007年11月24日放送

第31話「産地から届く母の味/ニセコ」
町の広報誌で見つけたひとつの記事。それが私に賑やかで暖かい出会いをもたらしてくれました。
15人の女性で構成されるサークル「じゅうごばぁ」。それぞれが受け継いできた味と知恵を駆使して地元の食材を使ったさまざまな料理に挑戦しています。
食材の旨みを引き立てるのは、おかあさんの味のぬくもり。15人のお母さんたちが集まって作り出す味には
15倍の優しさと、15人分の愛情が込められています。
ウィンターリゾート地として、今や海外からの注目度も高いニセコから「じゅうごばぁ」の味が世界に飛び出していく日が、まもなくやってきます。