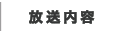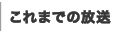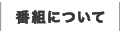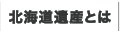NEXT
24:25
千鳥の相席食堂 芸能界随一の大御所ヒゲとHカップボイン▽スズメバチと(秘)命懸け死闘!
25:30
ダイアンのガチで!ごめんやす 【デビュー1周年記念ライブの企画を考えて】
26:00
アナちゃん
26:35
musicる TV 「緑黄色社会」ロングインタビュー!▼高校生ボカロP・takaken
27:05
ワールドプロレスリング 話題沸騰Yuto-Ice&OSKARのタッグ王座防衛戦!
27:35
テレビショッピング
04:05
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
テレビショッピング
04:45
元気に歩き続けるための秘訣を大公開
05:15
イチおし!プレミアム
05:45
アナちゃん
13:59字
ポツンと一軒家 豪快にイノシシ捕獲!離れて暮らす家族集まり笑顔で鉄板BBQ大会【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 政界はどう変わる?キーマンが生出演!
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 自然を守る?
17:55
ウェザータイム
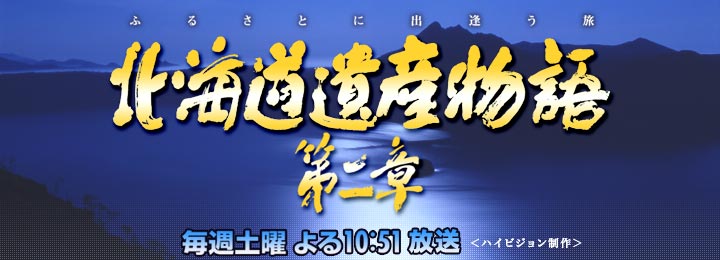

2009年2月7日放送

第90話「北海道文学百景(3)~伊藤整・極寒の小樽を愛した詩人」
月の明かりに青みを帯びる雪が、極寒の港町に舞う様。その情景をこよなく愛した作家の足跡を訪ねました。海風が地吹雪を起こす夜。小樽の町明かりが優しさを醸し出します。小樽商科大学の前身に学んだ伊藤整は、中学時代から詩を書き始めたといいます。処女作である詩集「雪明りの路」は、大自然が彩りを添えた豊かな感受性を言葉の中に封じ込めた秀作として著名な詩人たちからも称賛を浴びました。小樽の町を包む情緒には作家、伊藤整の青春も潜んでいるのでしょうか。「春待ち人」であったという伊藤整。春の喜びを何より引き立たせるからこそ作品の中に雪を散りばめたのかもしれません。
2009年1月31日放送

第89話「北海道文学百景(2)~有島武郎・農民に春を届けた博愛主義者」
季節が衣替えをする6月。ニセコでは一人の作家の命日を、最後の小説の名にちなんで「星座忌」と呼び、彼の功績に対する感謝の集いを催します。有島は何人も自然を私物化できないように農地もまた個人の所有物であってはならないと考えました。父から譲り受けた農場を農民たちが共有することを条件に無償で解放することを宣言。農地解放は、ニセコの大地に降り注ぐ陽光のように、小作人と呼ばれていた人達の未来を明るく照らし出しました。「生まれ出づる悩み」の作者、有島武郎が志したこと。それは、長い冬を耐えてきた人々に春の光を届けることであったのです。
厳しい冬を体験した者だけが知る春の喜び。その喜びを農地解放という形で農民に届けた有島武郎の功績は時を超えて語り継がれる北の大地の遺産です。大自然の中に広がる恵み豊かな農地は、博愛主義を貫く作家が農民に託した 自らの夢の種であったのかもしれません。
2009年1月24日放送

第88話「北海道文学百景(1)~有島武郎、夜学校に開花したヒューマニズム」
有島武郎が札幌農学校に入学したのは明治29年のことでした。新渡戸稲造の官舎に住み、農学校の自主独立の自由精神を信条とする当時の日本では異質の存在であった農学校で、自由闊達、博愛精神にふれながら札幌で青春時代を送りました。開放的な農学校の空気の中で、家庭の事情で学校に行けない青年を無料で 教える「遠友夜学校」でボランティア教師を務めます。この学校は後の国際連盟事務次長、新渡戸稲造が設立したもの。有島は夜学校の校歌を作詞し、7年間代表を務め、札幌でのボランティア活動の原点とも言える生活を送っていました。「北海道文学の父」と称される有島武郎。その原点には北海道開拓、国造りに燃える、若き青春の鼓動に満ちあふれていた時代があったのです。
2009年1月17日放送

第87話「もうひとつの北海道開拓(5)~希望の道標/吉野小学校閉校記念碑」
神の山に見守られてきた大地でひとつの歴史に幕が下りようとしています。教育に熱心であった入植者が開拓着手後すぐに作った小学校。 間もなく閉校するその学校に新たな命を吹き込もうとする一人の芸術家に出会いました。 新十津川町吉野地区。西には神の山と崇める「ピンネシリ」を臨む稲作地帯が広がります。 この町に開拓当初に作られた小学校が間もなくその1世紀以上の歴史にピリオドを打とうとしています。町の人の様々な思い出が詰まった小学校。そこに新たな命を吹き込もうとするアーティストがいました。作品の素材選びを始めた世界的芸術家の目に地元の自然石は欠かせないものに映ったようです。吉野小学校の閉校記念碑。鉄のフレームが切り取るのは神の山。そこに向かってまっすぐに伸びる103個の石が歴史の先に広がる希望への道標となるに違いありません。
2009年1月10日放送

第86話「もうひとつの北海道開拓(4)~開拓成就の喜びの味/金滴酒造」
この地では入植者が開拓に着手してから16年間禁酒の教えが守られていたといいます。 家族も集落も一体となってひたすら開拓に情熱を注いだ日々。努力と忍耐が実を結び、豊かに実ったお米と水に恵まれた地で飲酒に許しが出たのは開拓から17年目のことでした。 新十津川町に明治39年に設立された金滴酒造。雪清水が流れを作る川の伏流水。その清らかな水から生まれる味には開拓成就の喜びの歴史が刻まれています。 「自分たちが飲む酒は自分たちで造る」その思いから総勢81名の賛同者で作り上げた金滴酒造が今も貫く理念です。新十津川町でとれたお米と雪清水が作る川の伏流水で仕込まれる金滴酒造の日本酒。その深い味わいには忍耐の日々を超えて開拓を成就させた先人たちの喜びが隠されているのです。
2008年12月20日放送

第85話「もうひとつの北海道開拓(3)~第二の郷土・新十津川開拓」
新十津川町は、今年も実り豊かな一年を終えようとしています。入植者がこの大地に最初に鍬を下ろしたのは明治22年のことでした。奈良県十津川郷からの入植者たちは武士の出であったといいます。急勾配の山の斜面に畑が連なる十津川郷。険しい土地柄とは言っても住み慣れた地を離れ、新しい土地を開拓することができたのは…。 「さすが吉野の種なりと」この言葉の中に故郷への思いを力と誇りに変えて夢に向かった人々の姿が見えてくるのです。奈良県にある険しい山間の集落から村の守り神と共に新天地を求めてやってきた人々が北の大地に立派な第二の郷土を築いたのです。
2008年12月13日放送

第84話「もうひとつの北海道開拓(2) ~歴史の糸で結ばれた地/新十津川町と十津川村」
徳富川が町の中央を流れる新十津川町。ここに最初に入植した人たちは。明治22年に移住した初代のルーツを辿って見ました。奈良県吉野郡十津川郷の集落の一つ。険しい山間の地に、その歴史を紀元前まで遡ることのできる山の頂に鎮座する玉置神社があります。
玉置神社は、国を愛する心、つまり故郷を愛する心を時と場所を越えて十津川の血が流れる人々に伝えてきたのです。
感謝と思いやりの心。稲作地帯の風景の中に遠い山間の村の香りが潜んでいました。北海道開拓の歴史が1200キロも離れた村と町を目に見えない魂の糸でつないでいるのです。
2008年12月6日放送

第83話「もうひとつの北海道開拓(1)~北を目指した十津川人」
明治22年8月、奈良県吉野郡一帯を未曽有の豪雨が襲いました。中でも被害が大きかった十津川村は、3日間の雨量3,000ミリ、被害個所6,000か所、死者160人を出す、村が壊滅するほどの大災害となったのです。
その頃、北海道では、石狩平野の開拓は緊急課題とされており、また、ロシア南下への防衛対策から屯田兵の募集など、北海道への大移住計画が奨励されていました。
こうした時代背景のもと、新たな生活の地を求めた十津川村の5分の1にあたる、600戸2489人が、北海道への移住を決断しました。
「必ず第二の故郷を建設する」との固い意志を胸に秘めた村人たちは、はるか古から続く修験道である熊野古道を歩き、まだ見ぬ大地を目指し旅立ったのです。
2008年11月29日放送

第82話「秋の日高路(4)~風の町の漁日和」
白波が立つ海で漁を続ける人々。強風で木々さえまっすぐに立てないこの町では
風と付き合う術を知らずに生きてはいけないのです。大自然の狂気に触れる瞬間。人はその威力を目の当たりにして言葉を失い成す術もなく、その狂乱の時が過ぎてゆくのを待つしかありません。襟裳の風は人間の知恵と力の儚さを伝えるに十分なほど圧倒的な迫力を備えています。風が止み、海が凪ぐと襟裳の町は夜明け前から活気を見せ始めます。
風速10メートル以上の風が吹く日が1年の内に260日を超えるというこの町では
風のない日が漁日和。他の町では夏に終わる昆布漁がここでは10月半ばまで続くのも
漁に出られる日が少ないため。多少の風なら厭わず仕事を続けます。
風の町で天日にさらされる襟裳産昆布。
そこには自然の脅威とぬくもりの両方が凝縮された濃厚な旨みが詰まっているのです。
2008年11月22日放送

第81話「秋の日高路(3)~馬と夢に懸ける青春」
サラブレッドの生産育成牧場。日高には1000もの牧場があるといいます。
日々、馬の足馴らしを行う牧場スタッフ。365日馬と生活を共にし、輝くターフを、颯爽と駆け抜ける芸術品に育てます。そこで、“馬は「生活の一部」ではなく、「心の一部」”と話す若者に出会いました。馬と共に育ち、馬と共に生き、共に未来の夢にかける青年には馬のいない日常はありません。夜明けと共に、始まる厩舎の1日。初めて人を乗せる1歳馬の調教には細心の注意を必要とします。馬の心を知り尽くした職人しかできない仕事。
人と共に走ることを心地よいと感じ始めるサラブレッドたち。それは互いに心を通わせて初めてできること。馬の技量だけでも、人の技術だけでも完成させることはできません。
サラブレッドに囲まれてこの地で生きる若者には、情熱を注ぐ競技があります。
それもまた人馬一体で取り組むもの。「兄弟」と呼ぶ馬とともに「馬がいるから夢がある」
馬と共に駆ける少年の姿がそう語っていました。