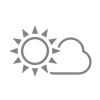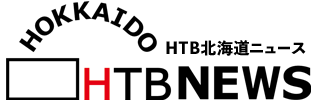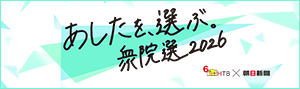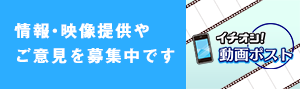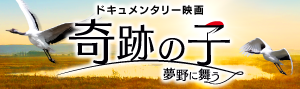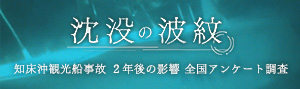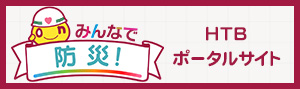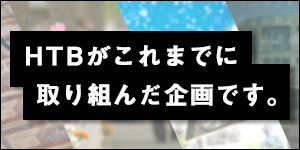「人への感染が近づきつつある」アメリカでは死者も…海鳥が大量死 いま北海道で何が起きているのか?
2025年 5月14日 18:18 掲載
《砂浜に広がる異様な光景》
■高橋海斗記者リポート「浜辺のいたるところに海鳥の死骸がうちあがっています。奥にあるのも海鳥の死骸ですね」
根室市長節の海岸。資料館の学芸員や野鳥の会が、海鳥の調査を続けています。今月8日、およそ2時間の調査で海鳥の死骸が10羽以上見つかりました。3月中旬から2か月近くの間に、見つかった死骸は600羽以上にのぼります。
■根室市歴史と自然の資料館外山雅大学芸員「異常という言い方が正しいのかわからないですけれども、ちょっといままでとは違う、いままでなかったことが起こっている」
過去に例のない海鳥の大量死。この海鳥たちを苦しめている原因は、高病原性鳥インフルエンザウイルスへの感染です。
《感染を繰り返し致死率の高いウイルスに》
■北海道大学大学院獣医学研究院迫田義博教授「鳥インフルエンザウイルスの中には高病原インフルエンザウイルスと低病原性インフルエンザウイルスと2種類ある。カモとかが持っている低病原性インフルエンザウイルスが養鶏場の中に入って、養鶏場の中でぐるぐる感染が繰り返されるうちに、アップグレードして高病原性インフルエンザウイルスに、ニワトリを100パーセント殺すウイルスに変わった」
カモ類が本来持っていたウイルスが、養鶏場など閉じた狭い空間で密飼いされているような家禽にうつり、次々と感染を繰り返す中で、鶏に対して致死率の高い高病原性のウイルスに変異しました。それが屋外に漏れて野鳥など自然界に広がりました。
感染すると呼吸器や脳の機能に障害が出て、急速に症状が進みます。2011年、浜中町でみつかった頭を振るオオハクチョウ。異常な行動を見せすぐに死にました。今年3月、根室市春国岱で撮影されたオオセグロカモメ。ふらつきながら倒れた瞬間です。この個体が高病原性鳥インフルエンザに感染していたかはわかっていませんが、専門家は典型的な症状だと指摘します。
■北海道大学獣医学研究院 迫田教授「首をぐるんぐるん振っている鳥っていうのは、肺でウイルスが増えてニワトリだったらコロッていくところを、脳もウイルスだらけの状況なんだけれども『僕は生き延びたい』という中で、脳の方でウイルスが増えちゃって、平衡感覚とかを失ってという状況なんです」
《世界中に伝播 感染は新たなフェーズへ》
ウイルスが拡散するイメージ図です。長距離を渡るカモやハクチョウなどが、夏は営巣地に集まり、冬は越冬地へ移動することを毎年繰り返すことで、ウイルスが世界中に運ばれました。それが数年前から新たなフェーズに入ったと迫田教授は指摘します。海外で海鳥や哺乳類に感染するケースが報告されはじめたのです。
先月18日根室市の海岸で発見されたゼニガタアザラシです。目が充血し、衰弱しています。まもなく死にましたが検査の結果、国内で初めて高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されました。さらに浜中町の海岸では絶滅危惧種の「ラッコ」が高病原性鳥インフルエンザと確認されました。根室市でも今月4日以降、ラッコ3頭の死骸が見つかりました。
■NPO法人エトピリカ基金片岡義廣理事長「まずいことが起きたなと思いました。
ここでも海鳥の死骸はあるんですよ。ラッコが遊んだりしている場面もあるので、3月下旬でも一回、そういう場面も見ましたから」
■北海道大学獣医学研究院 迫田教授「諸外国ではそういう海鳥の営巣地等で大量死があったり、そこで一緒に暮らしている野生の哺乳動物アザラシであったり、海外で起きているようなことが残念ながら国内でも発生が確認されたということ」
《アメリカで初の死者 意外な感染ルートとは》
そして今年1月。アメリカで初めて、高病原性鳥インフルエンザに感染した65歳の男性が死亡しました。CDC・疾病対策センターによりますと、男性は自宅の庭で飼っていたニワトリや野鳥と接触して感染したとみられています。アメリカでは去年1月から5月13日までに70人が感染し、その6割近くが実は「牛からの感染」です。乳牛に直接触れる酪農家が多く感染しているのです。
■北海道大学獣医学研究院 迫田教授「哺乳動物が大量にウイルスを浴びる、食べるとか、大量のウイルスに暴露されると鳥インフルエンザウイルスが哺乳動物にも感染する。しかし、もし触っちゃったとしても皆さんも新型コロナで覚えていると思うが、触った手からウイルスがぐりぐりと入り込むわけではない。触った手でこうやって(口などを)触る二次的な、この動作が良くないわけで、触っちゃったら手を洗うなりアルコール消毒でしっかりとしてもらえば、インフルエンザウイルスもコロナウイルスも秒殺です」
《“ウイルスという火の粉”…人への感染リスクが高まる》
日本ではまだ哺乳類の家畜の感染は確認されていません。迫田教授はヒトへの感染について過度な心配は必要ないとする一方で、今後、ウイルスとヒトとの距離は近くなっていく可能性があるとしています。
■北海道大学獣医学研究院 迫田教授「(ウイルスが)野鳥の中でもカモだけじゃなくて海鳥も、今度は野生動物もということになっていて、幸い日本ではないですけど、アメリカだったら乳牛で(感染)ということもあるわけじゃないですか。ウイルスの火の粉がいろんなところにいま飛んできている。だから一般の人たちが触れる機会が増えてきている。実際に我々人間とさらに近くなって、いわゆる鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染のリスクというのは高まっていくと思う」
《感染から身を守るために》
・野鳥の死骸や、衰弱している野生生物を見つけた場合、絶対に素手で触らない
・触った場合は手洗い、消毒
・犬や猫などのペットも注意が必要。
・そのまま放置すると他の動物などに食べられて、感染が拡大してしまう可能性があるので、住んでいる地域の振興局に連絡。