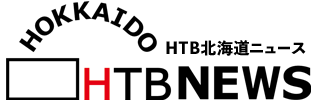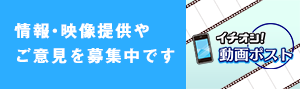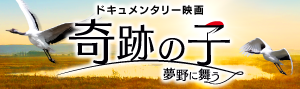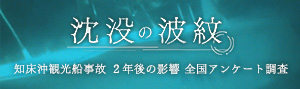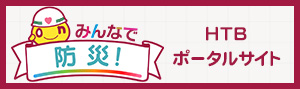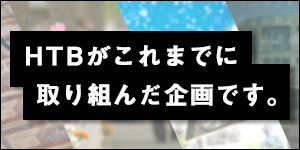「住む町に出産できる病院がない…」往復3時間を1人で運転して通院 妊婦サポートで自治体に開き
2025年 5月28日 12:42 掲載
人口が減少するのに伴い、地方の町で病院の数も減っています。「自分が住む町に、出産できる病院がない…」新しい命を迎え入れる地方都市の現状を取材しました。
■名寄市立総合病院・助産師・北田孝子さん「前回の健診から変わったことや気になることはどうですか?」
■澤田由生さん「変わったことは特にないけど、胸やけはまだあります」
■北田さん「しばらく赤ちゃんも大きくなっているから、子宮を持ち上げられての症状はしばらく続くかなと。ちょっと酸味のあるもの控えたりとか、食べてすぐ横にならないようにして気を付けていきましょう」
妊娠9ヶ月を迎えた澤田由生さん。お腹の中の赤ちゃんに会えるのは、来月末の予定です。この日は妊娠33週目の健診でした。赤ちゃんの成長も順調です。澤田さんが通っているのは、名寄市立総合病院。多くの診療科が集まる道北の基幹病院です。
■永山友菜記者「自宅は?どちらへ帰りますか?」
■澤田さん「枝幸町に帰ります」
■永山記者「少し遠いですよね」
■澤田さん「そうですね。片道1時間半かかるので」
澤田さんが住む道北の枝幸町では、1998年に出産を扱う病院がなくなりました。枝幸町から出産ができる最も近いマチが、90キロ離れた名寄市です。澤田さんは去年、夫の転勤のため、家族で札幌から枝幸町に引っ越しました。夫は平日に休みを取ることが難しく、頼れる身内もいません。2人目以降の出産では1人目よりもお産までの時間が早まる場合があります。澤田さんはこれまで札幌で3人、出産しました。今回は予定日の前に入院し、出産の誘発を行う「計画分娩」を選びました。3人の子どもが小学校やこども園に行っている間に半月に1、2度のペースで妊婦健診に通います。
■永山記者「お腹が大きくなってくると、車の乗り降りやシートベルトも大変ですよね」
■澤田さん「そうですね、このハンドルとの距離が詰められなくなってきちゃうので、そうするとペダルがギリギリになっちゃったりとか」
■永山記者「体調がいつ変わるか分からない中、一人で運転して通う不安は?」
■澤田さん「やっぱり、つわりとかあっても一人で運転しなきゃならないので。あと眠い、ホルモンバランスで眠くなったりとか、そういった中でも運転しなきゃいけない」
現在、出産できる病院があるのは北海道内179の自治体のうち、わずか27の市と町です。地域から病院が減った理由の一つは、出生数の減少です。70年前、一年に10万人を超えていた本道の出生数は、2000年に入って半減、2022年には2万6000人ほどに落ち込んでいます(グラフ)。出産を扱う病院は収入が減り経営難に陥ります。さらに去年導入された「働き方改革」で医師1人あたりが勤務できる時間が短くなりました。
■日本産科婦人科学会理事・旭川医科大学・加藤育民教授「多くの施設に先生方がいるということは難しいというふうになると、やはり患者さんも集めて、そして高度医療ができるようなスタッフも集めて提供する(医師の)数が沢山いる病院のほうが安全な医療を提供できるということを考えると、集約化というものは致し方ないという部分もあるかもしれません」
こうした事態を受けて道は2000年以降、札幌、帯広、釧路、函館の4カ所に、最も母子に危険が伴う分娩を扱う「総合周産期母子医療センター」を置き、その下に地域の医療を担う「地域周産期母子医療センター」を32か所、配置してきました(図)周産期とは出産前後の母子の命に関わるリスクが高まる期間のことです。「地域周産期母子医療センター」に位置付けられている名寄市立総合病院では、出産を扱っていない周辺の病院からカルテなどのデータを受け取り、32週以降の妊婦を引き継ぎます。このような体制を組むことで成果も出ています。
出産する年齢が35歳以上の「高齢出産」の割合です(グラフ)。リスクの高い高齢出産の割合が年々増えていますが、逆に周産期の子どもの死亡率は減少傾向となっています。しかし医療の集約が進む一方で遠くの病院に通わなければならない現状はかわりません。妊婦の負担を減らすためそれぞれの自治体がサポートや助成をおこなっています。深川市はハイヤーによる妊婦の送迎制度をはじめました。
■深川市・市民福祉部・主査・河崎かなえさん「市内のハイヤー事業所に妊婦さんの情報を事前に登録することで、陣痛が始まった妊婦の方をスムーズに医療機関に移送するための制度です」
2015年に出産できる病院がなくなった深川市は、2017年から陣痛が始まったときに、出産する病院へ妊婦をタクシーで送迎する制度を始めました。昨年度からは利用者の費用負担をなくし送迎運賃の全額を市が助成しています。
■深川市在住・タクシー送迎制度を利用し旭川で出産した人「上の子がいるので、結局日中は一時保育とかで預けられても、深夜の時間帯に陣痛がきてしまったら見てもらえる人がいないといけなくて、そうしたら主人は家にいなきゃいけなくて、ハイヤーがないと行けないので、とても安心材料になりました」
ただ妊婦のためのサポートは、補助の金額が少額だったり、そもそも支援制度がないなど、自治体によって開きがあります。
■澤田由生さん「枝幸町には陣痛タクシーはないと思います。タクシーの営業時間も枝幸町は決まっているんですよね。一応、計画出産の予定なので、そこまでに陣痛とかが来なければ安心して出産迎えられると思うんですけど、それまでにもし陣痛がきちゃったら大変かなっていうのはあります」
地域を支える次の世代が安心して生まれ育つ環境を作れるかどうか。それぞれのマチの姿勢が問われています。妊婦への支援については今月、厚生労働省の有識者検討会で、「出産費用の無償化」も含めた議論が始まっています。ただ病院の集約による長距離の通院の負担についてどのようなサポートがあるのか、注意深く見守っていく必要があると思います。医療過疎について今後もイチオシ!でお伝えしていきます。