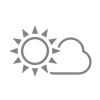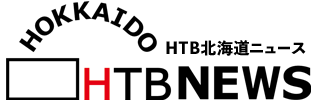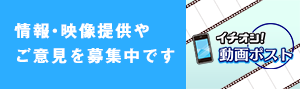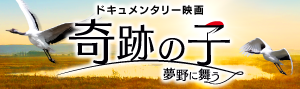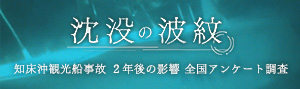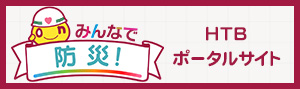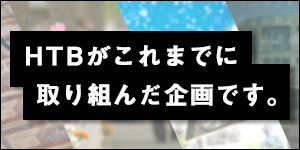廃業寸前から復活 小樽で120年以上の伝統をつなぐ…「国内最後」ガラス製の浮き玉工房
2025年 9月 2日 18:39 掲載
世界各地から観光客がガラスの工芸品を求めにぎわう小樽。この街で、120年以上続くガラス工房があります。
浅原宰一郎さん63歳。
明治からの歴史を持つ浅原硝子製造所の4代目です。
■浅原宰一郎さん:
「炉の温度は1240℃くらい。この上にもう一度ガラスを巻き取ってふくらませていきます」
造っているのは、漁業で使われる「浮き玉」。網を浮かばせ、目印にもなるガラス製の浮きです。まるい型に合わせて膨らませていきます。
大きいものは直径40センチほどになるといいます。
ガラス製の浮き玉。いま製造を行っているのは国内で宰一郎さんただひとりとなったといいます。
浮き玉の歴史は明治にはじまります。ニシン漁がにぎわいをみせていた時代、漁で使われていた浮きは木製でした。
■小樽市総合博物館・石川直章館長:
「日露争が終わった後、北洋漁業、カムチャツカ半島などでの漁業がとても盛んになっていきます。そちらの方で漁業をする場合、長い網が必要だし、波が荒いところなので浮力の大きな浮きが必要になってきます」
そこで生み出されたのがガラス製の浮き玉です。当時、小樽でガラス容器の製造を幅広く手掛けていた浅原硝子製造所に、道から依頼がありました。
■小樽市総合博物館・石川直章館長:
「大量に造らないといけないのである程度工場の規模を持っていないといけない。まずは浅原さんに委託をして造ったというのがはじまりと聞いています。」
1910年ごろ、初代・浅原久吉さんが日本で初めてガラス製の浮き玉を開発。道内の漁業の発展に大きく貢献しました。
しかし、1960年ごろになると安価で軽いプラスチック製の浮き玉が普及しはじめます。ガラス製の浮き玉の需要は徐々に減り、道内各地にあったという工場も閉鎖に追いこまれていきました。
宰一郎さんが生まれたのは、このころです。高校を卒業後、父親のもとに修業に入りましたが、3年で断念しました。
■浅原宰一郎さん:
「外の世界を見たかったというのは大きいのかなと思います」
時々職人として工房の手伝いに入ることもありましたが、サラリーマンとして、国内外のリゾートホテルや広告代理店などで様々な仕事を経験しました。工房を出て20年以上たった2007年、父である3代目の陽治さんが72歳で他界しました。宰一郎さんは当時、本州のリゾート施設で経営を支えていましたが、これを機に再び工房へと戻ることを決意します。
■浅原宰一郎さん(2007年・当時45歳):
「ずいぶん使っていなかったのでさびを落としています」
房宰一郎さんが4代目として戻ってきたとき、漁業用としてのガラス製の浮き玉の需要はすでにほぼ失われ、工房は生産中止の状態でした。
当時は勘を取り戻すのに手いっぱいだったといいます。
■浅原宰一郎さん(2007年・当時45歳):
「吹きガラスといってもすごく広くて深い。
自分がやっていた型吹きの浮き玉を造るということはごく一部の技術でしかないので、できないことの方が多かったです。浮き玉は造れるけどそれ以外のものは造ったことがなかったので勉強した。いろいろなものを造るために」
漁業用の浮き玉の製造はいまも続けらていますが、その数はごくわずか。
道内でこだわりのある漁師の注文にこたえています。工房を引き継いだ宰一郎さんは市場のニーズをとらえ、工芸品の制作や吹きガラス体験へ力をいれていきます。浮き玉にインテリアとしての価値を見いだし、浮き玉をベースにした一輪挿しや、照明カバーなどを生み出しました。
工房に、若い力も。高柳萌さん35歳。宰一郎さんの一番弟子です。
■浅原宰一郎さん:
「ぐにゅぐにゅの浮き玉ってこと?」
■高柳萌さん:
「そこまでぐにゅぐにゅじゃないけど、ちょっとねじってやります(固定する)」
ガラス工芸などを学んだ後、この工房で働きはじめた高柳さん。まだ浮き玉の製造には携われてはいませんが、色合いなど、自分なりのアイデアを積極的に試す日々です。
■浅原宰一郎さん:
「斬新なデザインを入れてやっている。それが結構いい感じです」
■高柳萌さん:
「考えたものを実際にやってみてうまくいけばよっしゃ、うまくいかなかったら何が悪かったのか反省しながらやっていっています。
お客さんが来た時にこれいいねと買ってくれるとすごいうれしいです」
浅原硝子製造所はことしで123年目。宰一郎さんは64歳になります。
■浅原宰一郎さん:
「動ける限りはやっていこうと思っていますが、現実問題そんな長くはもたないと思う」
弟子の高柳さんに託す思いもありますが、経営者としての苦悩に不安をこぼします。
■浅原宰一郎さん:
「ガラスを造るだけじゃない。経営者としての仕事も必要なので、そこを萌がどこまでカバーできるのかなというのはあったりします」
小樽を出て、さまざまな経験を重ねてきた宰一郎さん。
想いは原点にかえります。
■浅原宰一郎さん:
「ガラス屋の火を消したくないということです。吹きガラスの火を消したくない。浅原の火を消したくないという思い」