NEXT
09:55
おうちde 買いまSHOW
10:25
アナちゃん
13:45
テレビショッピング
13:50字
科捜研の女 #14【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #5【再】
21:48
ウェザータイム
24:15
千鳥の相席食堂 史上初!一度もボタン押さず!?芸能界のロケ達人▽千鳥脱帽(秘)ロケテク
25:20
ダイアンのガチで!ごめんやす 【バルーンアーティストを目指しませんか?】
25:50
アナちゃん
26:25
musicる TV 今勢いに乗る7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」総力特集
26:55
ワールドプロレスリング 新日本プロレス1.4東京ドーム!LDH武知海青が参戦!
27:25
テレビショッピング
27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
テレビショッピング
04:45
まるっと健康これ1杯青汁の魅力 徹底解明
05:15
イチおし!プレミアム
05:45
アナちゃん
06:00
キッズが見てる!もしもタレントじゃなかったら からし蓮根がショコラティエに挑戦!
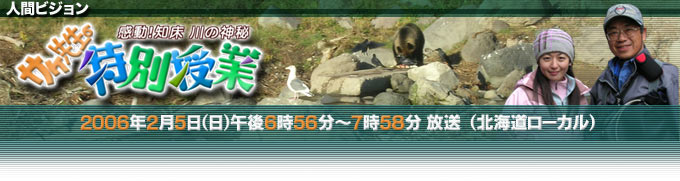
|
|
| 名前 |
- 知床のヒグマはサケをつかまえても卵(イクラ)しか食べない。
- ヒグマがよく石をひっくり返すのは、石の下にいるミミズを食べるため。
- サケの稚魚が川から海に出るのは夜である。
- サケが卵を産むときに、川底に穴を掘るのはメスの役割である。
- 女装するオスザケがいる。
- 1匹のメスザケが産む卵3,000個のうち、生まれた川に帰ってくるのはおよそ半分である。
- 厚化粧と薄化粧のメス。オスザケにモテモテなのは厚化粧のメス。
- 卵(イクラ)の色が赤いのはお母さんサケがエビをたくさん食べたから。
- 海でとれたサケよりも、川でとれたサケの方がおいしい。
- コケだらけの川とコケのない川。生き物が暮らしやすいのはコケのない川である。
- 知床のヒグマはサケをつかまえても卵(イクラ)しか食べない。
答え ×
ヒグマはサケの内臓やエラの部分を除いたほとんどの部分を食べます。ただし、サケが簡単にたくさんとれる時期は、好きな部分だけ(卵(イクラ)、頭の軟骨部分(氷頭 )、背中の筋肉など)を食べて、残りは捨ててしまうことがあります。 - ヒグマがよく石をひっくり返すのは、石の下にいるミミズを食べるため。
答え ×
アリを食べています。ヒグマは石や朽ちた木をひっくり返し、アリの巣を見つけてはなめるようにしてアリを食べます。夏の間、アリはクマの貴重なタンパク源となります。 - サケの稚魚が川から海に出るのは夜である。
答え ○
サケ先生が24時間、河口 に網をしかけて海に出る稚魚の数を数えた調査では、日が落ちた夜8時から10時の間が一番多く確認されました。稚魚は海鳥などの外敵から身を守るため、夜暗くなってから移動すると考えられています。知床ではシロザケの稚魚 は3月から8月の上旬にかけて川から海に旅立ちます。ピークは5月です。 - サケが卵を産むときに、川底に穴を掘るのはメスの役割である。
答え ○
オスザケはメスザケに穴を掘ることを促 すだけで、穴を掘ることはありません。メスは1~2日かけて、たたみ1帖分ほどの大きさの産卵床 を作り、その中に約3,000粒の卵が5カ所ぐらいに分けて産みこまれています。ときどき、メスが卵を産もうとしている時に他のオスが割り込んでこようとすると、尾びれで砂利を飛ばしてメスが掘った穴を埋めてしまうオスがいます。これは他のオスとの産卵をじゃまするためと考えられます。 - 女装するオスザケがいる。
答え ○
メスザケとなかなかカップルになれない弱いオス(=劣位 のオス)は、強いオスに攻撃されないよう体の模様をメスの模様に似せて(女装して)、既にカップルになっている強いオスとメスの間に割り込むことがあります。メスにカモフラージュすることで、強いオスの目をだまそうとするのです。 - 1匹のメスザケが産む卵3,000個のうち、生まれた川に帰ってくるのはおよそ半分である。
答え ×
戻ってくるのはおよそ2匹と言われています。1匹のメスが産んだ3,000個の卵のうち約600個くらいは稚魚になれずに死んでしまいます。約2,400個が稚魚になって海へ出て行きますが、他の魚に食べられたりして、無事生まれた川に戻って来るのはほんのわずかだけになってしまうのです。 - 厚化粧と薄化粧のメス。オスザケにモテモテなのは厚化粧のメス。
答え ○
川を上って子孫を残す準備が整ったサケには「婚姻色」と呼ばれるさまざまな模様が体の表面に表れます。メス同士の争いで卵を産む場所を勝ち取り、カップルになる資格のあるメスは、頭から尾にかけて黒いタテ線がくっきり現れます。つまり、この婚姻色が体にくっきり現れている「厚化粧」のメスザケは、「いつでも卵を産むことができますよ。バッチリ準備できていますよ」と周りに伝えているようなもの。子孫を残すのが最終目的となるサケの世界では、婚姻色がはっきり表われているほど人気の高いサケと考えられているのです。体の色の他に「体の大きいメス」もオスの人気が高いようです。
ちなみに、カップルの相手になることができた、つまりオス同士の争いで勝ち残った強いオスには、派手な赤紫色の雲状斑点が現れます。 - 卵(イクラ)の色が赤いのはお母さんサケがエビをたくさん食べたから。
答え ○
サケは北太平洋で主にオキアミ(甲殻類 /エビの仲間)などの動物プランクトンやクラゲを食べて育ちます。甲殻類をたくさん食べたサケから産まれた卵(イクラ)は赤みが強くなり、逆に甲殻類以外のものを多く食べたサケから産まれた卵(イクラ)は赤みが弱く、ピンクに近い色をしています。また、サケの身も稚魚の時は白く、海に出てから、赤い色素「アスタキサンチン」を持っている甲殻類を食べることによって、だんだん赤くなっていきます。 - 海でとれたサケよりも、川でとれたサケの方がおいしい。
答え ×
ごめんなさい。これは番組をよく見ても答えがわかりませんでしたね。
秋サケで一般的に食べられているのは、北海道や東北沿岸の海に設けられた定置網漁 で水揚げされたもの。川に戻ってきたサケは産卵直前になるにつれて体の脂が精子や卵(イクラ)に移動するなどして、身がパサパサの状態になってしまいます。ですから、一般的に人が食べておいしいと感じるのは「海」にいるサケになります。番組冒頭の秋サケ漁とおいしい鮭料理のシーンで伝えたかった情報ですが、うまくまとめることができませんでした。(プロデューサー沼田博光) - コケだらけの川とコケのない川。生き物が暮らしやすいのはコケのない川である。
答え ×
コケのある川です。コケのある川というのは川底が安定している証拠。急流によって川底の石が流されるような場所にコケは生えていません。川底が安定していると、生き物も安心して暮らせます。コケをエサにする昆虫、それを食べる魚、さらにそれを食べる鳥…たくさんの生き物が集まってきます。

| Copyright © HTB All Rights Reserved. |


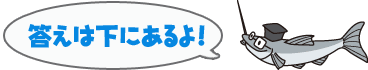 クマやサケに関する○×クイズです。
クマやサケに関する○×クイズです。






