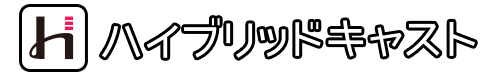過去の放送一覧
-
■2024年01月20日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
② 心不全に特化した診療チームがめざす医療】心不全は心筋梗塞や心臓弁膜症などの心疾患が原因して、心機能が低下する病態をいい、発症すると徐々に進行し治癒することはありません。北海道循環器病院の心不全チームでは、心不全が進行しても、住み慣れた自宅で過ごすことができるよう、地域の医療機関や訪問看護ステーションなどとICT端末で情報を共有しながら、連携、協働し、心不全患者さんの生涯を支える医療に取り組んでいます。心不全チーム 統括責任者 村上弘則先生にお話をお聞きしました。
-
■2024年01月13日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
① 心不全に特化した診療チームを開設した理由】高齢化の進展と共に心不全が急増しています。心不全は、狭心症や心筋梗塞、心臓弁膜症などが原因で心臓の機能が低下する病態です。番組では、数多くの心筋梗塞や心臓弁膜症などに対して開心術やカテーテル治療などを施行し、救命にあたってきた北海道循環器病院が心不全に特化した「心不全チーム」を開設した理由と、提供する医療について、大堀克己 理事長にお聞きしました。
-
■2023年12月23日放送【「5類」感染症となってはじめて迎える冬の生活
新型コロナウイルスのいま】新型コロナウイルスが5類に移行し初めて迎えるこの冬は、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が危惧されている。番組ではインフルエンザと新型コロナウイルスの感染の現状と、この秋から接種が始まったXBBワクチンの効果、感染予防対策等について感染症学会認定専門医がわかりやすく解説する。
-
■2023年12月16日放送【Presented by 日本ストライカー
加齢とともに増加する変形性関節症
③ 変形性股関節症の病態とロボット支援手術】骨盤と大腿骨をつなぐ股関節の軟骨が摩耗・変形することによって起こる「変形性股関節症」は進行すると、安静時の痛みなどから日常生活動作(歩行等)に大きな障害を与える。番組では「変形性股関節症」の病態、症状、治療、なかでも精密な手術が可能なロボット支援手術について日本整形外科学会認定専門医がわかりやすく解説する。
-
■2023年12月09日放送【Presented by 日本ストライカー
加齢とともに増加する変形性関節症
② 変形性膝関節症の病態とロボット支援手術】膝関節の軟骨や半月板が摩耗・変形することによって発症する「変形性膝関節症」は、高齢者の関節疾患で最も多いと推計されている。番組では「変形性膝関節症」の病態、症状、治療、なかでも精密な手術が可能なロボット支援手術について日本整形外科学会認定専門医がわかりやすく解説する。
-
■2023年12月02日放送【Presented by 日本ストライカー
加齢とともに増加する変形性関節症
①原因と対策】高齢化が進展するなかで要介助、要介護の原因のトップは整形外科疾患(関節疾患+ 骨折)で、認知症を超える。番組では3回シリーズで加齢とともに増加する変形性関節症について解説する。第一回は高齢者に多い関節疾患の原因と対策、治療について日本整形外科学会認定専門医がわかりやすく解説する。
-
■2023年08月19日放送【Presented by 大塚製薬
8月10日は手(ハンド)の日「あきらめないで!手指の悩み」
② 手指の病気と女性ホルモンとの関連】日本手外科学会が制定した8月10日「手(ハンド)の日」にちなんで行われた、HTB健康トーク「あきらめないで!手指の悩み」から2回シリーズで特集する。第二回は、手指の病気と女性ホルモンとの関連について、手外科の専門医が解りやすく解説する。
-
■2023年08月12日放送【Presented by 大塚製薬
8月10日は手(ハンド)の日「あきらめないで!手指の悩み」
① 手指の病気の原因と対策】日本手外科学会が制定した8月10日「手(ハンド)の日」にちなんで行った、HTB健康トーク「あきらめないで!手指の悩み」から2回シリーズで特集する。第1回は、手指の病気の原因と対策について、女性の更年期になぜ手指に障害が起こりやすいのか、手に障害が起きた時どう対応すべきなのか、手外科の専門医が分かりやすく解説する。
-
■2023年07月22日放送【医TVスペシャル「健康寿命と免疫の視点から~がん治療における免疫の可能性を探る~」】
BS朝日にて放送(7月22日 14時30分~15時00分)
高齢化が進展し、人生100年時代が目前に迫る中で、健康寿命の維持に「免疫」の関与が不可欠であることを解き明かすと共に、がん治療における「免疫」の可能性を解説する。 -
■2023年07月15日放送【新型コロナが5類に移行し 夏休みを前にして
④ 新型コロナ感染症に対するワクチンの効果】新型コロナ感染症が5類に移行し約2か月。行動制限等が緩和され、夏休みを前にした、新型コロナウイルスの感染の現状と、ワクチンの効果、感染予防対策等について解説する。
-
■2023年06月17日放送【新型コロナが5類に移行して
③「5類」移行後のワクチン接種】新型コロナ感染症が感染症法上5類に移行し、感染者数の発表や、療養制限、感染予防対策等が変化したが、2023年度のワクチン接種は従来通りの公費負担(自己負担なし)で行われる。番組では、ワクチンの作用メカニズムとともに、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方と、重症化リスクのない方へのワクチン接種の受け方等について解説する。
-
■2023年06月10日放送【新型コロナが5類に移行して ②
新型コロナ感染症に対するワクチンの効果】新型コロナ感染症が感染症法上5類に移行し、療養制限の緩和や、マスク着用などの予防対策が個人の判断に委ねられるようになった。番組では、5類移行後の新型コロナの正しい理解を目的として、新型コロナウイルスの変異株の現状と、ワクチンの作用メカニズム、重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある方になぜワクチン接種が勧奨されているのかを解説する。
-
■2023年06月03日放送【新型コロナが5類に移行して ①
新型コロナ感染症の現状とワクチン接種】新型コロナウイルス感染症が、2023年5月8日 感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類に移行し、感染者数の発表方法や、感染者等に対する療養制限等が大きく変化した。番組では、新型コロナが5類に移行したことによる注意点と、2023年5月に開始されたワクチン接種の対象と、その効果(目的)について解説する。
-
■2023年01月28日放送【正しく理解しよう「梅毒」②治療と予防】
前回に引き続き「梅毒」にスポットをあて、今回はその治療と予防について解説する。「梅毒」は2012年から顕著に増加しているが、その要因には2011年の緊急避妊薬の解禁と共に、治療を受けなくても一定の期間を経過すると症状が消失する、という「梅毒」の特徴的な症状が挙げられている。その特徴的な症状によって「梅毒」は潜在的な患者が自覚することなく性行為に及ぶことで感染を拡げてしまうため、番組では「梅毒」の初期症状の理解を高めると共に、「梅毒」の治療としてペニシリン系の抗菌薬が有効であることなどについて解説する。
-
■2023年01月21日放送【正しく理解しよう「梅毒」
①感染者数が増加する原因と特徴的な症状】「医TV」は今回から2回にわたって性感染症の一つである「梅毒」にスポットをあてる。「梅毒」は2012年から顕著に感染報告が増加しているが、その一因として、粘膜の接触を防ぐ、それまでの避妊方法であるコンドームに加えて、2011年に解禁された緊急避妊用のピルにより、粘膜の接触が増えたことなどが挙げられている。今回は「梅毒」の感染原因とともに、特徴的な症状である、未治療でも症状が一旦消失し、感染を拡げることなどについて解説する。
-
■2022年10月29日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
④ 心不全と上手に付き合うための心臓リハビリテーション】心不全の診療ガイドラインでは、心臓リハビリテーション(運動療法)は、運動耐容能(=運動できる力)の向上により、日常生活の動作や、生活の質の改善に効果があることが認められています。北海道循環器病院の心不全チームでは、運動を長期間継続するためには、患者さん相互が励ましあい、楽しみを感じられることが重要と考え、集団で行うリハビリ、北海道の自然を活かした独自の運動メニューを取り入れ、患者さんが主体的に運動に参加する意識の向上に取り組んでいます。
-
■2022年10月22日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
③ 心不全の在宅療養を支えるチームのチカラ】北海道循環器病院は循環器専門病院として、心筋梗塞や心臓弁膜症などの再発、進行により、心機能が低下する心不全が高齢化の進展と共に増加していることを受けて、心不全に特化した診療チーム(心不全チーム)を開設しました。心不全チームがめざす医療は「心不全が重症化しても住み慣れた自宅で、自分らしく生涯を過ごすことが出来るよう」支援すること。そのために、心不全チームでは、地域のかかりつけ医や、在宅医、訪問看護師などとICT(情報通信技術)端末で情報を共有しながら、連携・協働し在宅療養を支援しています。番組では、心不全の在宅療養における、在宅医や訪問看護師の活動や利用者の声を通して、心不全における在宅療養のチームのチカラの重要性について紹介します。
-
■2022年10月15日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
②心不全に特化した診療チームがめざす医療】「心不全」は心筋梗塞や心臓弁膜症などの心疾患が原因して、心機能が低下する病態をいい、発症すると徐々に進行し治癒することはありません。「北海道循環器病院」の心不全チームでは、心不全が進行しても、住み慣れた自宅で過ごすことができるように、地域の医療機関や訪問看護ステーションなどとICT端末で情報を共有しながら、連携、協働し、心不全患者さんの生涯を支える医療に取り組んでいます。
-
■2022年10月08日放送【北海道循環器病院「心不全チーム」の取り組み
① 心不全に特化した診療チームを開設した理由】高齢化の進展と共に心不全が急増しています。心不全は、狭心症や心筋梗塞、心臓弁膜症などが原因で心臓の機能が低下する病態です。番組では、数多くの心筋梗塞や心臓弁膜症などに対して開心術やカテーテル治療などを施行し、救命にあたってきた「北海道循環器病院」が心不全に特化した「心不全チーム」を開設した理由と、提供する医療について、大堀克己理事長に聞きしました。
-
■2022年09月24日放送【北海道から世界に向けて
消化器がんのロボット支援手術の第一人者
竹政伊知朗 教授がめざす医療②】札幌医科大学とHTBの連携企画「北海道から世界に向けて…消化器がんのロボット支援手術の第一人者 竹政伊知朗 教授のめざす医療」。 第二回は、大腸がんなどの消化器がんに対して、精密な手術が可能なロボット支援手術を普及させるために、竹政教授が中心として行った実施医の資格認定制度の見直しと、プロクター(指導医)による遠隔指導、遠隔手術について紹介する。
-
■2022年09月17日放送【北海道から世界に向けて
消化器がんのロボット支援手術の第一人者
竹政伊知朗 教授がめざす医療①】札幌医科大学が取り組む最新の医療が、道民の生活や地域医療にどのようにつながり、希望のある医療の未来につながるのかを解りやすく解説する札幌医科大学とHTBの連携企画。今回は「北海道から世界に向けて」と題して、消化器がんのロボット支援手術の第一人者 竹政伊知朗 教授のめざす医療を二週にわたって紹介する。
-
■2022年09月10日放送【膠原病に伴う間質性肺疾患】
「間質性肺疾患」は、肺でガス交換を行う肺胞の壁である「間質」が炎症により、線維化し硬くなる疾患。「肺線維症」または「間質性肺炎」とも呼ばれる。番組では、リウマチや、強皮症などを総称する「膠原病」という自己免疫疾患が原因で起こる「間質性肺疾患」について、北海道大学病院リウマチ・腎臓内科の渥美達也 教授が、その病態、診断や治療などについて分かりやすく解説する。
-
■2022年09月03日放送【新型コロナ 第7波の感染が高止まりを続けるなかで
② 医療用抗原検査キットによる自己診断と市販解熱剤の使用について考える】オミクロン株の変異株、BA.5は減少傾向にあると言われているが高止まりを続けている。番組では、発熱症状などで医療機関の受診や、救急車の要請が多いことなどを受けて、日本感染症学会、日本救急医学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本臨床救急医学会の4学会が発表した「医療機関の受診」「救急車の利用」に関する声明の中から、軽症で重症化リスクのない患者さんの自宅での医療用抗原検査キットによる自己診断と、市販の解熱剤の使用について紹介する。
-
■2022年08月27日放送【第7波の感染が高止まりを続けるなかで
① 新型コロナに感染したかもと思ったときの対応】オミクロン株の変異株、BA.5は、従来のBA.2に比べて感染力が高く、第7波の感染が高止まりを続けているなかで、医療関係者が感染し診療に影響が出ている医療機関が増加していることから、日本感染症学会、日本救急医学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本臨床救急医学会の4学会は、医療機関の受診、救急車の利用に関する緊急提言を2022年8月2日に発表した。番組では、日本プライマリ・ケア連合学会の理事長が運営する北海道家庭医療学センター 栄町ファミリークリニックの中川貴史院長に、提言にある「新型コロナに感染したかもと思ったときの対応」についてお話を伺った。
-
■2022年07月16日放送【社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院】
アレルギー性結膜疾患の患者さんの約85%は花粉性アレルギー性結膜炎と推定されている。 番組では、アレルギー結膜疾患等の炎症性疾患を専門分野とする、愛心メモリアル病院・眼科 /名誉顧問の大野重昭先生が、アレルギー性結膜疾患の原因、分類、診断、治療等について解説する。
-
■2022年07月09日放送【社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院】
「愛心メモリアル病院」では、増加する糖尿病の三大合併症に対応するため、2021年10月に「糖尿病内科」を開設し、従来から設置していた循環器内科、心臓血管外科、腎臓内科、血液透析内科、眼科と「糖尿病チーム」を組織し対応にあたっている。番組では同病院眼科の「糖尿病網膜症」への対応について紹介する。
-
■2022年07月02日放送【社会医療法人社団愛心館
愛心メモリアル病院 眼科】高齢化の進展により増加傾向にある白内障にスポットをあてる。白内障とはカメラのレンズに相当する水晶体が白濁し、視力障害を生じる疾患。発症早期であれば薬物療法で進行を抑えることはできるが、進行した白内障を薬物療法で改善することは困難。番組では、新しく眼科部長に就任した 金 学海 先生が、白内障の病態と共に白内障の治療として有効な眼内レンズ挿入について紹介する。
-
■2022年04月02日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療③加齢黄斑変性】3回シリーズで展開する「北広島おぎの眼科」が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療。第3回は「加齢黄斑変性」について考える。「加齢黄斑変性」は加齢などが起因し、網膜の中心部の黄斑が障害され視力が低下する病気。番組では「北広島おぎの眼科」が取り組む、超広角・無散瞳レーザー検眼鏡や広角OCT(光干渉断層計)による精度の高い診断や、「加齢黄斑変性」の主たる治療である「抗VGEF薬」による硝子体への注射療法などについて紹介する。
-
■2022年03月26日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療
②糖尿病網膜症】「北広島おぎの眼科」が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療。第2回は「糖尿病網膜症」について考える。「糖尿病網膜症」は糖尿病患者の増加と共に、顕著に増加し日本人の中途失明の原因の第2位。番組では「北広島おぎの眼科」が取り組む迅速で精度の高い診断と共に、低侵襲な「硝子体手術」等について紹介する。
-
■2022年03月19日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療
①白内障に対する眼内レンズ挿入】「医TV」は今週から3週にわたって「北広島おぎの眼科」が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療について紹介する。第1回は水晶体が白濁することで光が乱反射し、霞がかかったような症状などがみられ、日常生活に影響がある場合に行うことが推奨される「眼内レンズ挿入手術」について、専門医がわかりやすく解説する。