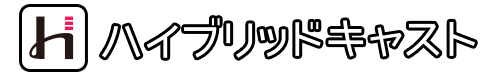過去の放送一覧
-
■2020年07月04日放送【特集企画「新型コロナ」によるフレイル予防
③体幹の筋力低下を予防する運動】特集企画「新型コロナによるフレイル予防」第3回は、体幹の筋力低下を予防する運動にスポットをあてる。新型コロナウイルスによるデイサービスの休止などは、運動をする機会がなくなり、フレイルといわれる心身機能の低下につながる。番組では、家庭で安全にできる、タオルを使用した体幹の筋力低下を予防する運動ついて紹介する。
-
■2020年06月27日放送【特集企画「新型コロナ」によるフレイル予防
②下肢筋力の低下を予防する運動】特集企画「新型コロナによるフレイル予防」第2回は、下肢筋力の低下を予防する運動 にスポットをあてる。新型コロナウイルスによるデイサービスの休止などは、高齢者 が運動をする機会がなくなり、フレイルといわれる心身機能の低下につながる。番組 では、安全に運動を行う姿勢、準備運動とともに、家庭で下肢筋力を維持する簡単な 運動について紹介する。
-
■2020年06月20日放送【特集企画「新型コロナ」によるフレイル予防
① 家庭で安全に運動を行うための準備運動】新型コロナウイルスの感染拡大にともない、介護サービスの利用を自粛する利用者や、休業する介護サービス施設も現れている。その影響を受け、自宅から出ることが出来ず、体を動かす機会が減少することで、心身機能が低下したフレイルといわれる状態の高齢者が増えている。医TVではフレイル予防の特集企画を4回シリーズで放送する。第1回は、家庭で安全に運動を行うための準備運動にスポットをあてる。
-
■2020年06月13日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
⑥治療薬の最新事情】新型コロナウイルス感染症の治療薬は、エボラ出血熱に対するレムデシビルが保険承認されたが、それ以外では新型インフルエンザに対するアビガン等、他の疾患で承認され、新型コロナウイルスに効果が期待できる薬剤の臨床治験が進んでいる。番組では、新型コロナウイルス感染症の重症化のメカニズムと共に治療薬の最新事情について札幌医科大学 横田伸一教授が解説する
-
■2020年06月06日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
⑤診断の最新事情】新型コロナウイルス感染症は、PCR検査の際の唾液からの検体採取や、迅速診断キットによる抗原検査が保険承認されるなど、診断分野において顕著な進歩を遂げている。番組では、新型コロナウイルス感染症の診断の最新事情について札幌医科大学 横田伸一教授が解説する。
-
■2020年05月30日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
④正しい受診の仕方】新型コロナウイルスの感染者が増加し「医療崩壊」という言葉が現実味を帯びる中で、医療スタッフの献身的なサポートにより収束傾向に向かいつつあるとされている。しかし、緊急事態宣言が解除された地域では再燃の傾向もある。番組では、地域医療を支える医師会の視点から、感染が疑われる際の正しい受診の仕方について、北海道医師会 長瀬 清会長が解説する。
-
■2020年05月23日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
③ 新型コロナウイルス感染症の予防】新型コロナウイルス感染症が全国的に収束状態に向かい休業要請が緩和される中で、外出や人との接触等が少しずつ増える傾向にある。本企画では第二波、第三波の感染予防の視点から、日常生活上での感染予防のポイントについて札幌市保健所 山口亮 感染症担当部長が解説する。
-
■2020年05月16日放送【特集企画「食生活と疾病」
高血圧を予防する「酢」の可能性】生活習慣病の中で最も患者数が多く、約4,300万人と推計される高血圧。別名「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれ、高血圧が長期間継続することによって動脈硬化が進展し、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクが高くなると言われている。番組では、高血圧予防のポイントとして減塩の重要性を取り上げ、美味しさを保ちながら減塩を進めることができる酢の効果と、ポン酢・ポン酢しょうゆ等の活用法について紹介する。
-
■2020年05月09日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
② 新型コロナウイルス感染症の症状と重症化の要因】新型コロナウイルス感染症は、発熱やせき、倦怠感など風邪に似た症状がひとつの特徴と言えるが、感染者の中には自覚症状のない方も相当数いることが明らかとなり、感染が広がった一因とされている。番組では、新型コロナウイルス感染症の注意すべき症状と、重症化の要因とともに、風邪のような症状が見られた場合には、医療者への感染を防ぐためにも、受診前にかかりつけ医や、帰国者接触者相談センターに連絡し指示を受けて受診することの重要性について札幌市保健所 山口亮 感染症担当部長が解説する。
-
■2020年05月02日放送【正しく理解しよう「新型コロナ」
① コロナウイルスの種類と感染経路】日本国内でも感染が広がり、社会活動や経済活動に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症。医TVでは、正しく理解しよう「新型コロナ」と題して、新型コロナウイルスの特徴や、感染経路、症状、医療崩壊を防ぐためのポイントをわかりやすく紹介する。第一回は、新型コロナウイルスの特徴、種類、感染経路について、札幌医科大学 横田伸一教授が解説する。
-
■2020年04月25日放送【沢井製薬プレゼンツ
「かかりつけ医」の認知症対応能力を向上させるために...
「認知症サポート医」の役割とは?】高齢化の進展と共に、認知症の方は顕著に増加傾向にあります。そうした中、国は「認知症になっても出来る限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現をめざす」様々な施策を推進しています。そのためには、地域医療を支える「かかりつけ医」の認知症対応能力の向上が不可欠であり、国は認知症サポート医の養成を進めています。番組では、認知症サポート医の役割等について紹介します。
-
■2020年04月18日放送【大塚製薬プレゼンツ
知られていない!? 女性の手や指の痛みなどの原因】手や指は男性女性を問わず、生活や仕事で絶えず使い続けていることから、腱鞘炎や手根管症候群などで整形外科を受診する人は多い。しかし、最近手や指の痛みやこわばりの原因が、女性ホルモンの減少により起こることが明らかとなった。番組では、そのメカニズムと共に、女性ホルモンの減少により生じる、様々な症状の改善に効果が期待できるエクオールについて紹介する。
-
■2020年04月11日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療
③加齢黄斑変性】北広島おぎの眼科が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療。第3回は加齢黄斑変性について考える。加齢黄斑変性は加齢などが起因し網膜の中心部の黄斑が障害され視力が低下する病気。番組では北広島おぎの眼科が取り組む無散瞳レーザー検眼鏡や、OCT(光干渉断層計)による精度の高い診断や、加齢黄斑変性の主たる治療である抗VGEF薬による注射療法などについて紹介する。
-
■2020年04月04日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療
②糖尿病網膜症】北広島おぎの眼科が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療。第2回は糖尿病網膜症について考える。糖尿病網膜症は糖尿病患者の増加と共に顕著に増加し日本人の中途失明の原因の第3位。番組では北広島おぎの眼科が取り組む迅速で精度の高い診断とともに、低侵襲な硝子体手術等について紹介する。
-
■2020年03月28日放送【正しく理解しよう
C型肝炎 注目される飲み薬による治療】肝炎とは肝臓を構成する肝細胞が壊れ、肝臓本来の働きである「代謝」「解毒」「胆汁の合成・分泌」が低下した状態。日本人の肝炎ではウイルス性肝炎が最も多く、慢性肝炎へ移行する肝炎で最も多いのがC型肝炎ウイルスによる肝炎。番組では、C型肝炎ウイルスの感染経路、診断、最近注目される飲み薬による治療について、日本肝臓学会認定専門医が解説する。
-
■2020年03月21日放送【北広島おぎの眼科
患者さんのニーズに応える低侵襲治療 ①
白内障に対する眼内レンズ挿入】北広島おぎの眼科が取り組む、患者さんのニーズに応える低侵襲治療について紹介する。第一回は白内障に対する眼内レンズ挿入。白内障は高齢化の進展と共に増加し80歳以上高齢者のほぼ100%が罹患していると推計される。番組では水晶体が白濁することで光が乱反射し、霞がかかったような症状などがみられ、日常生活に影響がある場合に行うことが推奨される、眼内レンズ挿入手術について紹介する。北広島おぎの眼科は多焦点眼内レンズ挿入手術については厚生労働省の先進医療施設の認定を受けていることから、民間医療保険の先進医療特約に加入していれば手術料は保障の対象となる。
-
■2020年03月14日放送【正しく理解しよう「睡眠時無呼吸症候群」
③ 社会的影響と治療について考える】医TVは 3回シリーズで交通事故等のリスクを増加させる「睡眠時無呼吸症候群」にスポットをあてる。睡眠時無呼吸症候群は昼間の強い眠気や、倦怠感や疲労感により集中力が続かない等の症状がみられることから、交通事故のリスクが健常者の約7倍である他、作業効率の低下やミスの増加から企業の業績に大きな影響を与える。第三回は睡眠時無呼吸症候群による社会的影響を軽減するためのCPAP(シーパップ)治療等について紹介する。
-
■2020年03月07日放送【正しく理解しよう「睡眠時無呼吸症候群」
② 検査と診断について考える】医TVは 3回シリーズで生活習慣病の重症化につながる「睡眠時無呼吸症候群」にスポットをあてる。睡眠時無呼吸症候群は就寝中に起こることから患者さん自身が気づくことが難しい疾患。第二回は睡眠時無呼吸症候群患者と健常者の交通事故や循環器系疾患の合併症リスク比較とともに、医療機関受診の契機、重症度を判定するための検査等について紹介する。
-
■2020年02月29日放送【正しく理解しよう「睡眠時無呼吸症候群」
① 原因と起こり得る合併症について考える】生活習慣病の重症化に関与する「睡眠時無呼吸症候群」にスポットをあてる。第一回は、睡眠時無呼吸症候群の原因と起こり得る合併症について考える。睡眠時無呼吸症候群は睡眠時に起こる病態であることから患者さん自身が気づくことが難しい疾患。番組では、睡眠時無呼吸症候群の原因として最も多い、閉塞型のメカニズムと共に、睡眠時無呼吸症候群が背景にある生活習慣病や起こり得る合併症について紹介する。
-
■2020年02月22日放送【医療法人ハートフル会
札幌駅前ペリオ・インプラントオフイス】30歳以上の約80%が歯周病に罹患し、歯を失う原因の約40%が歯周病といわれる。しかし、歯を失うことは、顎への刺激を激減させ顎の骨を痩せさせる原因となりインプラントを埋入することができないことも多い。番組では全歯欠損に対するインプラント治療と共に、顎の骨が痩せた場合の骨造成等について紹介する。
-
■2020年02月15日放送【医療法人ハートフル会
札幌駅前ペリオ・インプラントオフイス】高齢化の進展と共に増加する歯周病により歯を失い、噛むことが出来なくなった場合のインプラントの治療について、一歯欠損など事例をもとに手術の負担の少ないテンプレートガイド下によるインプラント治療について紹介する。
-
■2020年02月08日放送【社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院】
糖尿病網膜症は糖尿病による高血糖が長期間続くと、目の網膜の血管の閉塞や出血等が起こる病態で「単純網膜症」「増殖前網膜症」「増殖網膜症」に大別される。番組では、増殖前網膜症を増殖網膜症に進行させないために、新生血管を焼灼し出血等を防ぐレーザー光凝固術について紹介する。
-
■2020年02月01日放送【沢井製薬プレゼンツ
正しく理解しよう「ロコモティブシンドローム」】ロコモティブシンドロームといわれる(通称:ロコモ)運動器症候群は、骨や関節、筋肉など運動器の障害によって、移動機能が低下し日常生活に影響する状態をいい、日本人の要支援、要介護の原因の第一位となっている。ロコモの原因は、加齢による筋力、持久力などの身体機能の低下と、関節や骨などの運動器の疾患。番組では、ロコモのセルフチェックや、ロコモ予防等について紹介する。
-
■2020年01月25日放送【GME医学検査研究所(高崎市登録衛生検査所)】
群馬県高崎市の登録衛生検査所として郵送検査に取り組む、GME医学検査研究所について紹介する。GME医学検査研究所で行う郵送検査は、多くの方に検査の機会を提供し、異常が認められた場合には迅速に医療機関を受診することを目的とする。郵送検査の主なものは、心疾患・脳血管疾患のリスク検査(NT-proBNPについて精査)と、性感染症検査。GME医学検査研究所では、検査希望者に検査キットを郵送し、少量の血液などを採取し返送された検体を、免疫自動分析装置やリアルタイム遺伝子増幅法等を用い、感度の高い検査を行っている。
-
■2020年01月18日放送【社会医療法人愛心館 愛心メモリアル病院】
高齢化の進展や、糖尿病等合併症として増加傾向にある「白内障」にスポットをあてる。「白内障」とはカメラのレンズに相当する水晶体が白濁し、視力障害を生じる疾患。発症早期であれば薬物療法で進行を抑えることはできるが、進行した「白内障」を薬物療法で改善することは困難。番組では、「白内障」の病態と共に「白内障」の対症治療として有効とされる眼内レンズ挿入について紹介する。
-
■2020年01月11日放送【医療法人社団つばさ会
やまはな皮フ科クリニック】「やまはな皮フ科クリニック」は地域の方たちに喜ばれる皮膚科医療の提供をめざしてクリニック開設時から、夜間診療や土・日曜診療とともに、病気や障害等の理由で外来通院が困難な方を対象とした訪問診療(札幌市全域を対象)を行っています。
-
■2019年12月21日放送【国家公務員共済組合連合会 斗南病院】
2019年12月の医TVは、クリスマスやお正月を前にして、食生活などが原因する病気にスポットをあてる。第三回は、胆のう結石に対する腹腔鏡手術と、総胆管結石に対するERCP(経皮経肝的胆管結石除去術)について紹介する。
-
■2019年12月14日放送【国家公務員共済組合連合会
斗南病院】2019年12月の医TVは、クリスマスやお正月を前にして、食生活などが原因する病気にスポットをあてる。第二回は「胆石症」。胆石症は大別すると胆のう結石、総胆管結石に分類される。番組では胆石症の原因となる食生活や、症状、治療方針等について紹介する。
-
■2019年12月07日放送【国家公務員共済組合連合会
斗南病院】2019年12月の医TVは、クリスマスやお正月を前にして、食生活などが原因する病気にスポットをあてる。第1回は「脂肪肝」。脂肪肝は特徴的な自覚症状がなく、気付かぬままに進行し脂肪性肝炎や肝硬変になって発見されることも多い。番組では脂肪肝を早期発見するための診断とともに、治療薬のない脂肪肝の改善策等について紹介する。
-
■2019年11月30日放送【高齢者の注意すべき感染症
③帯状疱疹の原因と予防】医TVは、高齢者が注意すべき感染症を3回シリーズで紹介する。第三回は帯状疱疹の原因と予防。帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスが原因。小児期にかかった水痘(水ぼうそう)が治っても、ウイルスは体内の神経節に休眠し、高齢などによって免疫が低下することでウイルスが覚醒し痛みや発疹、水泡などの症状が出現する。番組では、帯状疱疹の注意すべき症状と予防法等について紹介する。