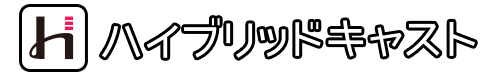過去の放送一覧
-
■2019年04月27日放送【正しく理解しよう「結核」①
結核の感染経路と症状】今回から「医TV」は、近年、集団感染など再興感染症として感染患者が増加する「結核」を3回シリーズで紹介する。第一回は「結核」の感染経路と注意すべき症状。「結核」は結核菌が空気感染や飛沫感染で感染が拡大する感染症で高齢者に感染者が多い。その理由は、高齢者は昭和25年前後、日本人の死亡原因の第1位が「結核」であった頃に感染し、発症しなかった「潜在性結核感染症」であったことに起因する。番組では「潜在性結核感染症」が「活動性結核」に進行するプロセスと「結核」の注意すべき症状について紹介する。
-
■2019年04月20日放送【正しく理解しよう「風しん」②風しんの予防】
正しく理解しよう「風しん」の第二回は予防について考える。「風しん」は、小児と比べ大人が罹患すると重症化する傾向が高いが、多くは1週間程度で治癒する。しかし、20週以内の妊婦が感染すると胎児の目や耳、心臓等に異常が生じる「先天性風しん症候群」となることが多い。番組では、2019年13週現在、感染の拡大が継続するなかで、国が2019年4月から3か年に限定し進める、予防接種を打っていない(一定期間に出生した)男性に対する「風しん」の追加対策等について紹介する。
-
■2019年04月13日放送【正しく理解しよう「風しん」
①感染拡大の原因と対策】2018年後半から関東地方で感染が拡大した「風しん」を2週にわたって紹介する。「風しん」は、風しんウイルスに飛沫・接触感染することで発症する急性発疹性感染症。感染すれば免疫を獲得し、二度と発症することはないが、1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性は「風しん」の予防接種を行っていなかったため、「風しん」に感染したことがない人を中心に昨年から感染が拡大し、2019年は13週段階で1,000人を超える感染が報告されている。番組では、「風しん」の特徴的な症状とともに、妊婦が感染することで胎児に障害が生じる可能性がある「先天性風しん症候群」についても紹介する。
-
■2019年04月06日放送【沢井製薬プレゼンツ「医療のチカラプロジェクト」
静岡型・地域包括ケアシステムについて考える】高齢化が進展するなかで、国は「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らすことができるように」地域包括ケアシステムを推進しているが、理解している生活者は少ない。番組では市民の理解を高めるために地域包括ケアシステムを「自宅でずっと」プロジェクトとして展開する、「静岡型・地域包括ケア」について紹介し、在宅医療と介護の連携について考える。
-
■2019年03月30日放送【正しく理解しよう「胆石症」③
国家公務員共済組合連合会 斗南病院】2019年3月の「医TV」は脂質や糖質の多い食事等に起因する消化器病スポットをあてる。 第五回は「胆石症の腹腔鏡手術と内視鏡治療」。「胆石症」は大別すると胆のう結石、総胆管結石に分類される。番組では胆のう結石に対する「腹腔鏡手術」と、総胆管結石に対する「ERCP(経皮経肝的胆管結石除去術)」について紹介する。
-
■2019年03月23日放送【国家公務員共済組合連合会 斗南病院】
2019年3月の「医TV」は脂質や糖質の多い食事等に起因する消化器病スポットをあてる。 第四回は「胆石症の診断と治療」。胆石症は大別すると胆のう結石、総胆管結石に分類される。番組では胆のう結石や総胆管結石の痛みや、感染による症状とともに、診断・治療について紹介する。
-
■2019年03月16日放送【正しく理解しよう「胆石症」①胆石症の原因と症状
国家公務員共済組合連合会 斗南病院】2019年3月の「医TV」は脂質や糖質の多い食事等に起因する消化器病にスポットをあてる。 第三回は「胆石症の原因と症状」。「胆石症」は、「胆のう結石」、「総胆管結石」、「肝内結石」に分類され、脂質やコレステロールの多い食事等が原因で発症する。番組では結石のできるメカニズムや、「胆石症」の痛みの特徴などについて紹介する。
-
■2019年03月09日放送【正しく理解しよう「脂肪肝」②脂肪肝の診断と治療
国家公務員共済組合連合会
斗南病院】2019年3月の医TVは脂質や糖質の多い食事等に起因する消化器病にスポットをあてる。 第二回は「脂肪肝の診断と治療」。脂肪肝は特徴的な自覚症状がなく、気付かぬままに進行し脂肪性肝炎や肝硬変になって発見されことも多い。番組では脂肪肝を早期に発見するために必要な検査・診断とともに、治療薬のない脂肪肝の改善策等について紹介する。
-
■2019年03月02日放送【正しく理解しよう「脂肪肝」①脂肪肝の原因と症状
国家公務員共済組合連合会
斗南病院】2019年3月の「医TV」は脂質や糖質の多い食事等に起因する消化器病にスポットをあてる。第一回は「脂肪肝の原因と症状」。脂肪肝については、以前、重症化しない病気と考えられていたが、現在は脂肪性肝炎から肝硬変や肝臓がんに進行する注意すべき病気と考えられている。番組では、脂肪肝の原因である脂質の多い食事やアルコールがどのようなメカニズムで脂肪肝に進展するか等とともに、その症状について紹介する。
-
■2019年02月23日放送【社会医療法人社団愛心館
愛心メモリアル病院】2019年2月の「医TV」は「心不全」にスポットをあてる。第四回は「心不全に対する緩和ケア」について紹介する。「緩和ケア」は一般の方の多くが、がん治療においてのみ行われていると思われているが、「心不全」においても日常生活動作時の呼吸困難や息切れなどの症状がQOLの低下につながることから「緩和ケア」の関与の重要性が叫ばれている。本回では「心不全における緩和ケア」の目的等について紹介する。
-
■2019年02月16日放送【社会医療法人社団愛心館
愛心メモリアル病院】2019年2月の医TVは「心不全」にスポットをあてる。第三回は心不全に対する薬物療法と運動療法(心臓リハビリ)について紹介する。過去において、心不全に対する運動は禁忌とされていたが、近年では筋力を高めることで運動耐容能が向上し、心機能を補助する働きがあることが明らかになった。番組では心不全に対する運動療法の効果等について解説する。
-
■2019年02月09日放送【社会医療法人社団愛心館
愛心メモリアル病院】2019年2月の「医TV」は「心不全」にスポットをあてる。第二回は「高血圧」や「脂質異常症」、「糖尿病」等の生活習慣病に起因して進行する「心不全」の重症度別による自覚症状とともに、「心不全」の診断に必要な検査について紹介する。
-
■2019年02月02日放送【社会医療法人社団愛心館
愛心メモリアル病院】2019年2月の医TVは「心不全」にスポットをあてる。「心不全」は病名ではなく高血圧や不整脈、狭心症等が起因して心臓のポンプ(収縮・拡張)機能に異常をきたし、血液循環が障害される病態、状態。第一回は心不全の原因疾患と注意すべき症状等について紹介する。
-
■2019年01月26日放送【医療法人ハートフル会
札幌駅前ペリオ・インプラントオフイス】30歳以上の約80%が歯周病に罹患し、歯を失う原因の約40%が歯周病といわれる。しかし、歯を失うことは、顎への刺激を激減させ顎の骨を痩せさせる原因となりインプラントを埋入することができないことも多い。番組では全歯欠損に対するインプラント治療と共に、顎の骨が痩せた場合の骨造成等について紹介する。
-
■2019年01月19日放送【医療法人ハートフル会
札幌駅前ペリオ・インプラントオフイス】高齢化の進展と共に増加する歯周病により歯を失い、噛むことが出来なくなった場合のインプラントの治療について、一歯欠損など事例をもとに手術の負担の少ないないテンプレートガイド下によるインプラント治療について紹介する。
-
■2019年01月12日放送【正しく理解しよう
「救急車が到着するまでの対応」】全国的に119番通報から病院収容までの時間が顕著に遅延しているなかで、心肺停止の状態において1分間心肺蘇生を行わなければ約7~10%救命率が低下するとされる。現在119番通報から救急車の現場到着までは約8.5分であり、その間、心肺蘇生を行わなければ救命率は0~5%と激減する。本企画では救急車到着までに傷病者の身近にいる(バイスタンダー)の対応すべき行動について紹介する。
-
■2018年12月15日放送【正しく理解しよう「高血圧」
⑤ 血圧と脈拍管理の重要性について考える】家庭血圧計には最高血圧、最低血圧とともに脈拍が表示されるが、多くの方が血圧の数値を注視し、脈拍については関心が低い。成人の安静時の脈拍は60~70回/分。しかし、脈拍は生活習慣病に起因した不整脈等の疾患のチェックには不可欠であり、脈が速くても、遅くても、疾患が背景にあると推測される。番組では脈拍異常の原因と対応等について紹介する。
-
■2018年12月08日放送【正しく理解しよう「高血圧」
④危険な夜間高血圧と早朝高血圧について考える】サイレントキラーと言われる高血圧は、冬の季節はヒートショックにより脳卒中や心筋梗塞等を合併しやすく注意が必要といわれる。番組では高血圧の中でも特に危険な「夜間高血圧」と「早朝高血圧」の原因と早期発見のための家庭血圧の測定の重要性について紹介する。
-
■2018年12月01日放送【医療法人社団宏仁会
平岡皮膚科スキンケアクリニック】皮膚は人体最大の臓器で疾患も数多い。今回の「医TV」は「患者さんの皮膚を健康にしたい」との願いを持って一般皮膚科診療と共に、美容皮膚科診療(自由診療/全額自己負担)に取り組む「平岡皮膚科スキンケアクリニック」を紹介する。
-
■2018年11月24日放送【Presented by 沢井製薬
福岡県医師会診療情報ネットワークとびうめネット
ICT(情報通信技術)を活用した診療情報の共有について考える】高齢化が進むなかで、国は要介護が必要になっても住み慣れた地域で生涯を過ごすことができるよう、地域包括ケアシステムの充実に取り組んでいる。そのためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援が機能的に連携することが重要であり、診療情報等の共有は不可欠。番組では「福岡県医師会」が主管する「とびうめネット」の取り組みを通して、多職種が連携するためにはどのように「ICT(情報通信技術)」を活用すべきかを、実際の使用例から考える。
-
■2018年11月17日放送【正しく理解しよう「インフルエンザ」
③インフルエンザの診断と治療について考える】秋から冬の季節にかけて流行するインフルエンザは、高熱が出ても発症後12時間はウイルス量が少なく迅速診断でも判定が難しい。第三回はインフルエンザの診断方法とともに、抗インフルエンザ薬による治療と治療時における注意点について紹介する。
-
■2018年11月10日放送【正しく理解しよう「インフルエンザ」
②インフルエンザの予防について考える】「医TV」は秋から冬の季節にかけて流行するインフルエンザを3回シリーズでスポットをあてる。 第2回はインフルエンザの原因や感染経路と共に、予防について流行前から流行初期のワクチン接種、流行期のマスク着用や手洗いうがいの励行の他、日常生活での感染予防等を紹介する。
-
■2018年11月03日放送【正しく理解しよう「インフルエンザ」 ①
インフルエンザとは?かぜとは?】今月の「医TV」は3回シリーズで「インフルエンザ」にスポットをあてる。第1回はインフルエンザとかぜの違いについて紹介する。インフルエンザはインフルエンザウイルスによって発症する感染症であり、気温が低下し湿度が低下する秋~冬季に流行するのに対して、かぜは、コロナウイルスなどにより、通年通して発症する感染症であることが大きな差異。本企画では、感染経路と共にインフルエンザの特徴的症状、起き得る合併症等について紹介する。
-
■2018年10月27日放送【正しく理解しよう「漢方治療」
風邪と葛根湯の作用について考える】秋も深まり、冬の季節が目前に迫る中で、かぜと葛根湯の作用にスポットをあてる。風邪はウイルス感染症であり、冬の季節は空気が乾燥することでウイルスの感染が広がりやすい。本企画では、風邪のウイルスの感染のメカニズムと共に、葛根湯の生薬の成分や効能とともに、効果的な服薬について紹介する。
-
■2018年10月20日放送【特集企画「健康寿命と牛乳のチカラ」
②牛乳摂取が糖尿病予防にいい根拠】食欲の秋、是非知っておいてほしい「健康寿命と牛乳のチカラ」を2週にわたって特集する。第2回は「牛乳摂取が糖尿病予防にいい根拠」と題して、ご飯だけを摂取するよりも、ご飯を食べた後に牛乳を摂取したほうがGI値と言われる血糖上昇指数が緩やかとなることや、牛乳摂取と糖尿病の発症リストに関する疫学研究の結果等について紹介する。
-
■2018年10月13日放送【特集企画「健康寿命と牛乳のチカラ」
①牛乳と脳卒中予防をめぐる新事実】食欲の秋、是非知っておいてほしい「健康寿命と牛乳のチカラ」を2週にわたって特集する。第一回は「牛乳と脳卒中予防の新事実」と題して、脳卒中の原因である高血圧に対する牛乳の降圧効果とともに、世界的な疫学研究等による牛乳の定期摂取と脳卒中等の発症リスク低下について紹介する。
-
■2018年10月06日放送【正しく理解しよう「認知症」
②住み慣れた地域で認知症と上手に付き合うために】「第37回日本認知症学会学術集会」が札幌で開催されることから、道民への認知症の正しい理解を高めるための啓発企画を二週にわたって展開する。第二回は、少子高齢化が進む中、認知症患者を、地域全体で見守っていく「地域包括ケア」について、「砂川モデル」として全国的に注目を集める中空知地域を例に、その取組みを紹介する。
-
■2018年09月23日放送【正しく理解しよう「認知症」
① 認知症の予防と早期発見の重要性について考える】「第37回日本認知症学会学術集会」が札幌で開催されることから、道民への認知症の正しい理解を高めるための啓発企画を二週にわたって展開する。第一回は、高齢化の進展とともに増加する認知症のリスク因子とともに、認知症を早期に発見し、適切な治療を行うことなどにより認知症進行を抑制できることなどについて紹介する。
-
■2018年09月16日放送【正しく理解しよう「高血圧」
③高血圧を改善する生活習慣と治療について考える】9月の医TVは「高血圧」にスポットをあてる。高血圧の原因に塩分の過剰摂取が挙げられるが日本人は塩分が大好きな民族。第三回は、サイレントキラー(忍び寄る殺人者)といわれる高血圧を改善する生活習慣と治療について紹介する。
-
■2018年09月09日放送【正しく理解しよう「高血圧」
② 高血圧の合併症について考える】9月の医TVは「高血圧」にスポットをあてる。第二回は、サイレントキラー(忍び寄る殺人者)といわれる高血圧の合併症について考える。厚生労働省の患者調査によれば高血圧患者は約1010万人と推計されているが医療機関を受診し治療を受けている方は68万人で約942万人は「高血圧を自覚していない」か」「高血圧を指摘されていても自覚症状がないことから医療機関を受診していない」という。本企画では死に至る危険性の高血圧が引き起こす合併症とその対策について紹介する。